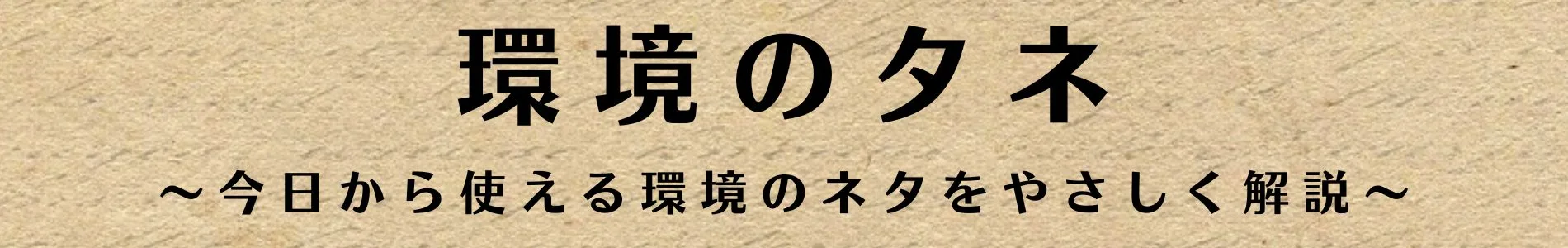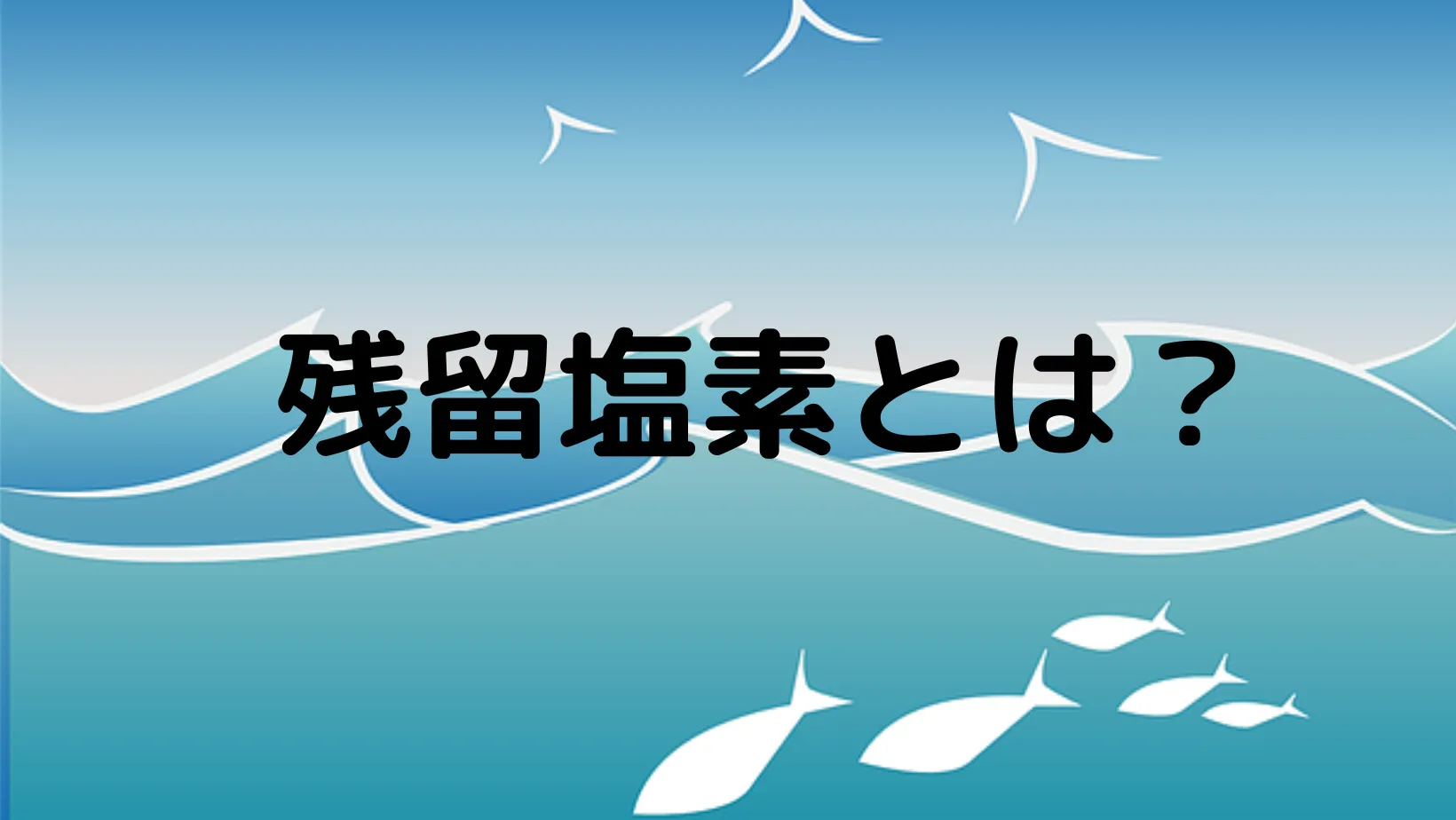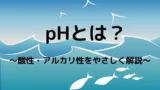水道水に含まれる「残留塩素」は、安全を守るために欠かせない一方で、カルキ臭などが気になるという声も少なくありません。本記事では、残留塩素の基準値や人体への影響をわかりやすく解説し、プールや井戸水との違い、家庭でできる測定方法や除去のコツを紹介します。

水道水に関わる身近なテーマをわかりやすく解説します。
※ 本ページはプロモーションが含まれています
残留塩素とは?水道水に入っている理由と役割
残留塩素とは、水道水の消毒のために加えられた塩素が、蛇口まで届いた時点でまだ残っているものをいいます。日本の水道法では、安心して飲めるように一定量の残留塩素を維持することが決められています。水道水は配水管を通る間にさまざまな環境にさらされますが、塩素が残っていることで細菌の繁殖を防ぎ、安全な状態を保ちながら家庭まで届けられます。
- 残留塩素=水道水に残る消毒用の塩素
- 目的は細菌の繁殖防止と安全性確保
- 水道法で一定量を維持することが義務化
残留塩素の基準値【水道水・井戸水・プールの比較】
水道法では、蛇口から出る水に含まれる遊離残留塩素は0.1mg/L以上、1.0mg/L以下であることが定められています。浄水場では消毒のために塩素が添加され、配水管を通って家庭まで届く間に細菌が繁殖しないよう管理されています。
家庭で使う小さな井戸水では、法律の義務はないものの、衛生状態によって塩素消毒が必要とされ、残留塩素の有無を確認することが欠かせません。
また、プールは飲用ではありませんが、多人数が利用するため、国の規則に基づき、水道水より高めの0.4~1.0mg/L程度で管理されています。
- 水道水:0.1~1.0mg/Lが基準
- 井戸水:消毒が必要な場合は残留塩素の確認必須
- プール:0.4~1.0mg/L程度で維持
遊離残留塩素とは、殺菌力を持つ「次亜塩素酸(HClO)」や「次亜塩素酸イオン(ClO⁻)」が水中に残っている状態を指します。ppmとmg/Lは同じ単位を表します。
(参考)環境省|水道水質基準について
残留塩素が人体に与える影響
水道水の塩素濃度では、人の健康への影響はありません。世界保健機関(WHO)のガイドラインでは、体重60kgの人が1日に2リットルの水道水を一生飲み続けても健康に影響がない濃度を「5mg/L以下」としています。日本の基準値はこの水準を大きく下回っており、安全性が確保されています。
- 水道水の塩素濃度では人の健康に影響はない
- 日本の基準値はWHOが示す安全水準よりはるかに低い
(参考)千葉県|千葉県営水道
残留塩素が低いとどうなる?高いとどうなる?
残留塩素の濃度が低すぎると、大腸菌などの細菌が繁殖しやすくなり、水の安全性が損なわれるおそれがあります。一方で濃度が高いと、カルキ臭が強く出て飲みにくさを感じることがあります。
なお浄水器などで塩素を除去した水は、細菌の抑制効果が弱まるため保存に向かず、早めに使い切ることが大切です。水道水は通常、基準範囲内で安定して管理されており、日常生活で心配する必要はほとんどありません。
- 低いと細菌が繁殖しやすくなる
- 高いとカルキ臭が強くなる
- 浄水器で除去した水は保存せず早めに使用
残留塩素の測定方法と家庭用検査キット
残留塩素の簡単な検査は、ご家庭でも手軽に測定できます。もっとも簡単なのは試験紙やチェッカーで、数秒で色の変化から濃度を確認できます。
より正確さを求める場合は、パックテストやDPD法が使われ、数値として把握できます。最近ではデジタル式の測定器や、個人向けの検査キットも市販されており、日常的な水質チェックに役立ちます。
- 試験紙・チェッカー:安価で初心者にも扱いやすい
- パックテスト・DPD法:精度が高く、比較実験にも活用できる
- デジタル測定器・家庭用キット:繰り返し利用でき、数値管理に便利
補足:市販の検査キットは通販やホームセンターでも入手可能です。浄水器の効果を確認したいときや、井戸水を安心して利用したいときに役立ちます。

主に水道水の残留塩素を測れる検査キットをご紹介します
水道水から残留塩素を除去する方法
残留塩素が気になる場合は家庭でも簡単に減らす方法があります。もっとも一般的なのは浄水器で、活性炭フィルターによってカルキ臭や塩素を取り除けます。煮沸も有効で、蓋を開けながら5分以上沸かし続けると塩素が揮発します。さらに、レモン汁などビタミンCを加えることで塩素を中和する方法もあります。
- 浄水器(活性炭フィルター)で除去
- 煮沸による塩素の揮発
- レモン水(ビタミンC)による中和

塩素を取り除いた水は長期保存に適さないため、早めに飲み切りましょう。
残留塩素と他の水質指標との違い
水質を評価するには、残留塩素だけでなくさまざまな指標を組み合わせて考えることが大切です。残留塩素は水にどの程度の殺菌力が保たれているかを示すものです。一方で、濁度や色度は水の透明さや色合いといった見た目を示し、硬度やpHは味や飲みやすさに関わる要素です。性質の異なる指標をバランスよく確認することで、水の安全性と快適さの両方を判断できます。
- 残留塩素=消毒の指標
- 濁度・色度=見た目の清浄度
- 硬度・pH=味や飲みやすさの要素
※pHに関してこちらの記事で詳しく解説しています
よくある質問(FAQ)
Q1:残留塩素はゼロにした方が安全ですか?
A1:残留塩素をゼロにすると細菌が繁殖しやすくなり、水の安全性が保てません。そのため水道法では、蛇口の水に0.1mg/L以上を必ず残すように定められています。
Q2:赤ちゃんのミルクに水道水(残留塩素入り)を使っても大丈夫ですか?
A2:水道法の基準値内であれば健康に影響はなく、赤ちゃんにも利用できます。気になる場合は、浄水器や煮沸で塩素を取り除いてから使うと安心です。
Q3:プールの残留塩素が水道水より高いのはなぜですか?
A3:プールは多くの人が利用し、水質が短時間で変化しやすいためです。衛生を守るために、水道水よりも高めの0.4~1.0mg/L程度で管理されています。
Q4:家庭で残留塩素を測る方法はありますか?
A4:市販の試験紙やチェッカーを使えば数秒で確認できます。より正確に測りたい場合は、パックテストやデジタル測定器を使う方法もあります。
Q5:水道水のカルキ臭が気になるときの対処法は?
A5:カルキ臭は残留塩素によるものです。浄水器を使う、5分以上煮沸して蓋を開けておく、レモン汁などビタミンCを加えるといった方法で軽減できます。
まとめ
残留塩素は、水を安心して使うために必要なものです。基準値は法律で定められており、日本の水道水は世界的にも安全な水準に管理されています。測定や除去の方法を知っておけば、より安心して水を利用できます。今日の暮らしに欠かせない残留塩素を正しく理解し、上手に付き合っていきましょう。
- 残留塩素は水道水に残る消毒用の塩素で、安全確保に必要
- 水道水は0.1~1.0mg/L、井戸水やプールも用途ごとに基準がある
- 日本の基準値はWHOの安全基準を大きく下回り、健康上問題ない
- 濃度が低いと細菌繁殖、高いとカルキ臭が強くなるが通常は安定
- 試験紙・パックテスト・デジタル計など家庭で簡単に測定できる
- 浄水器・煮沸・レモン水で塩素を減らせるが保存には注意が必要
- 濁度・硬度・pHなど他の指標とあわせて総合的に判断することが大切
もっと知りたい方におすすめの本

水に関わる本を3冊ご紹介します。
『図解でわかる 14歳からの水と環境問題』(インフォビジュアル研究所)
水と環境をテーマに、図やイラストを交えて解説した入門書。環境問題や水の役割を、視覚的に理解しやすい構成になっています。
『今日からモノ知りシリーズ トコトンやさしい水道の本』(日刊工業新聞社)
水道の仕組みや歴史、技術をわかりやすく紹介。専門知識がなくても読み進められ、水道の全体像を把握するのに役立ちます。
『水道民営化で水はどうなるのか』(岩波ブックレット)
水道事業の民営化をめぐる仕組みや課題を解説。水の安全性や公共サービスのあり方について考えるきっかけとなる内容です。
卓上アクリル元素周期表(おまけ)
最後におまけですが、化学関連のインテリアアイテムとして、机に置いて楽しめる卓上アクリル元素周期表をご紹介します。