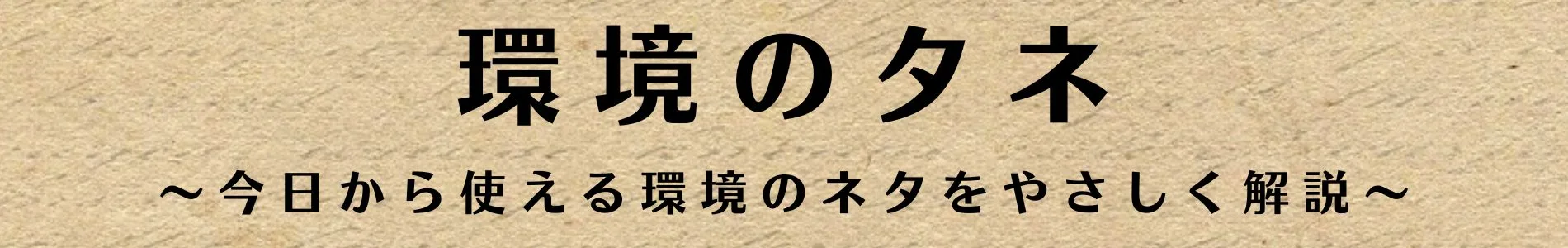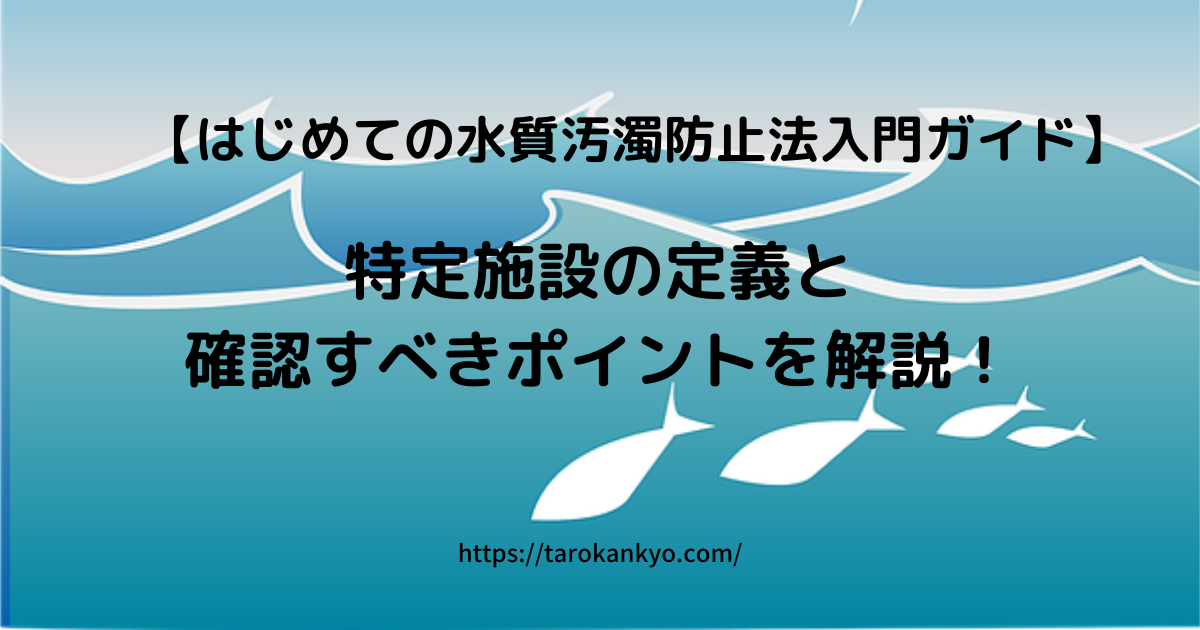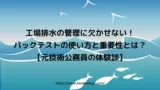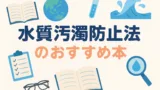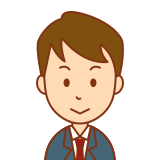
工場の水質汚濁防止法の担当者になったけど、「特定施設」って何??実は、よくわかっていないんだよね。。

今回はこんな悩みを解決します。
例えば、こんな方におすすめです
・特定施設の概要をわかりやすく知りたい方
・工場の水質汚濁防止法を担当する新任者
・新しく特定事業場の経営者・工場長になる方
・公害防止管理者を受検する予定の方 など
本記事では、水質汚濁防止法の特定施設のポイントをわかりやすく解説しています。「担当者は何をすればいいのか?」がわかるようにまとめたので、現場で役立ててください。
・水質汚濁防止法の元行政職(元公務員技術職)
・公害防止管理者(水質第1種)の有資格者
水質汚濁防止法のおススメの本は、こちらの記事が参考になります。
特定施設だけでなく全体を理解したい場合は、以下の記事をご覧ください。
「水質汚濁防止法をわかりやすく解説!はじめて届出担当者になったら最初に確認すべき5点」
※法の解釈は自治体判断になります。実際の運用には、お住いの自治体にご相談ください。
※本記事で引用している条文や特定施設一覧は、法改正などにより更新されていることもあります。最新版は原文を確認してください。
水質汚濁防止法の特定施設とは?

特定施設の定義
特定施設の定義は、水質汚濁防止法第2条第2項に規定されています。要約すると、こんな施設です。
特定施設とは、汚水や廃液を排出する政令で定めた施設のこと
つまり、汚れた水や廃液を扱うような施設で、政令(水質汚濁防止法施行令)で定めた施設のことです。
特定施設を設置していると(設置予定も含む)、水質汚濁防止法の規制対象になります。
水質汚濁防止法 第2条(抜粋)
e-Gov 水質汚濁防止法
2 この法律において「特定施設」とは、次の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。
一 カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質(以下「有害物質」という。)を含むこと。
二 化学的酸素要求量その他の水の汚染状態(熱によるものを含み、前号に規定する物質によるものを除く。)を示す項目として政令で定める項目に関し、生活環境に係る被害を生ずるおそれがある程度のものであること。
特定施設一覧
具体的にはどんな施設でしょうか?
政令(水質汚濁防止法施行令)別表第一にズラリと規定されていますが、汚水や廃液を扱うような施設はほぼ網羅されているのではないでしょうか。
※たくさんあるので、見たい方だけ、下のところをクリックして開いてください。
別表第一(第一条関係)
一 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 選鉱施設
ロ 選炭施設
ハ 坑水中和沈でん施設
ニ 掘削用の泥水分離施設
一の二 畜産農業又はサービス業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 豚房施設(豚房の総面積が五〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
ロ 牛房施設(牛房の総面積が二〇〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
ハ 馬房施設(馬房の総面積が五〇〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
二 畜産食料品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 原料処理施設
ロ 洗浄施設(洗びん施設を含む。)
ハ 湯煮施設
三 水産食料品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 水産動物原料処理施設
ロ 洗浄施設
ハ 脱水施設
ニ ろ過施設
ホ 湯煮施設
四 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 原料処理施設
ロ 洗浄施設
ハ 圧搾施設
ニ 湯煮施設
五 みそ、しよう油、食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、ソース又は食酢の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 原料処理施設
ロ 洗浄施設
ハ 湯煮施設
ニ 濃縮施設
ホ 精製施設
ヘ ろ過施設
六 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設
七 砂糖製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 原料処理施設
ロ 洗浄施設(流送施設を含む。)
ハ ろ過施設
ニ 分離施設
ホ 精製施設
八 パン若しくは菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈でんそう
九 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機
十 飲料製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 原料処理施設
ロ 洗浄施設(洗びん施設を含む。)
ハ 搾汁施設
ニ ろ過施設
ホ 湯煮施設
ヘ 蒸留施設
十一 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 原料処理施設
ロ 洗浄施設
ハ 圧搾施設
ニ 真空濃縮施設
ホ 水洗式脱臭施設
十二 動植物油脂製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 原料処理施設
ロ 洗浄施設
ハ 圧搾施設
ニ 分離施設
十三 イースト製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 原料処理施設
ロ 洗浄施設
ハ 分離施設
十四 でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 原料浸せき施設
ロ 洗浄施設(流送施設を含む。)
ハ 分離施設
ニ 渋だめ及びこれに類する施設
十五 ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 原料処理施設
ロ ろ過施設
ハ 精製施設
十六 麺類製造業の用に供する湯煮施設
十七 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設
十八 インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設
十八の二 冷凍調理食品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 原料処理施設
ロ 湯煮施設
ハ 洗浄施設
十八の三 たばこ製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 水洗式脱臭施設
ロ 洗浄施設
十九 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ まゆ湯煮施設
ロ 副蚕処理施設
ハ 原料浸せき施設
ニ 精練機及び精練そう
ホ シルケツト機
ヘ 漂白機及び漂白そう
ト 染色施設
チ 薬液浸透施設
リ のり抜き施設
二十 洗毛業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 洗毛施設
ロ 洗化炭施設
二十一 化学繊維製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 湿式紡糸施設
ロ リンター又は未精練繊維の薬液処理施設
ハ 原料回収施設
二十一の二 一般製材業又は木材チツプ製造業の用に供する湿式バーカー
二十一の三 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設
二十一の四 パーテイクルボード製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 湿式バーカー
ロ 接着機洗浄施設
二十二 木材薬品処理業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 湿式バーカー
ロ 薬液浸透施設
二十三 パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 原料浸せき施設
ロ 湿式バーカー
ハ 砕木機
ニ 蒸解施設
ホ 蒸解廃液濃縮施設
ヘ チツプ洗浄施設及びパルプ洗浄施設
ト 漂白施設
チ 抄紙施設(抄造施設を含む。)
リ セロハン製膜施設
ヌ 湿式繊維板成型施設
ル 廃ガス洗浄施設
二十三の二 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 自動式フイルム現像洗浄施設
ロ 自動式感光膜付印刷版現像洗浄施設
二十四 化学肥料製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ ろ過施設
ロ 分離施設
ハ 水洗式破砕施設
ニ 廃ガス洗浄施設
ホ 湿式集じん施設
二十五 削除
二十六 無機顔料製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 洗浄施設
ロ ろ過施設
ハ カドミウム系無機顔料製造施設のうち、遠心分離機
ニ 群青製造施設のうち、水洗式分別施設
ホ 廃ガス洗浄施設
二十七 前号に掲げる事業以外の無機化学工業製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ ろ過施設
ロ 遠心分離機
ハ 硫酸製造施設のうち、亜硫酸ガス冷却洗浄施設
ニ 活性炭又は二硫化炭素の製造施設のうち、洗浄施設
ホ 無水けい酸製造施設のうち、塩酸回収施設
ヘ 青酸製造施設のうち、反応施設
ト よう素製造施設のうち、吸着施設及び沈でん施設
チ 海水マグネシア製造施設のうち、沈でん施設
リ バリウム化合物製造施設のうち、水洗式分別施設
ヌ 廃ガス洗浄施設
ル 湿式集じん施設
二十八 カーバイト法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 湿式アセチレンガス発生施設
ロ 酢酸エステル製造施設のうち、洗浄施設及び蒸留施設
ハ ポリビニルアルコール製造施設のうち、メチルアルコール蒸留施設
ニ アクリル酸エステル製造施設のうち、蒸留施設
ホ 塩化ビニルモノマー洗浄施設
ヘ クロロプレンモノマー洗浄施設
二十九 コールタール製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ ベンゼン類硫酸洗浄施設
ロ 静置分離器
ハ タール酸ソーダ硫酸分解施設
三十 発酵工業(第五号、第十号及び第十三号に掲げる事業を除く。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 原料処理施設
ロ 蒸留施設
ハ 遠心分離機
ニ ろ過施設
三十一 メタン誘導品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ メチルアルコール又は四塩化炭素の製造施設のうち、蒸留施設
ロ ホルムアルデヒド製造施設のうち、精製施設
ハ フロンガス製造施設のうち、洗浄施設及びろ過施設
三十二 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ ろ過施設
ロ 顔料又は染色レーキの製造施設のうち、水洗施設
ハ 遠心分離機
ニ 廃ガス洗浄施設
三十三 合成樹脂製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 縮合反応施設
ロ 水洗施設
ハ 遠心分離機
ニ 静置分離器
ホ 弗ふつ素樹脂製造施設のうち、ガス冷却洗浄施設及び蒸留施設
ヘ ポリプロピレン製造施設のうち、溶剤蒸留施設
ト 中圧法又は低圧法によるポリエチレン製造施設のうち、溶剤回収施設
チ ポリブテンの酸又はアルカリによる処理施設
リ 廃ガス洗浄施設
ヌ 湿式集じん施設
三十四 合成ゴム製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ ろ過施設
ロ 脱水施設
ハ 水洗施設
ニ ラテツクス濃縮施設
ホ スチレン・ブタジエンゴム、ニトリル・ブタジエンゴム又はポリブタジエンゴムの製造施設のうち、静置分離器
三十五 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 蒸留施設
ロ 分離施設
ハ 廃ガス洗浄施設
三十六 合成洗剤製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 廃酸分離施設
ロ 廃ガス洗浄施設
ハ 湿式集じん施設
三十七 前六号に掲げる事業以外の石油化学工業(石油又は石油副生ガス中に含まれる炭化水素の分解、分離その他の化学的処理により製造される炭化水素又は炭化水素誘導品の製造業をいい、第五十一号に掲げる事業を除く。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 洗浄施設
ロ 分離施設
ハ ろ過施設
ニ アクリロニトリル製造施設のうち、急冷施設及び蒸留施設
ホ アセトアルデヒド、アセトン、カプロラクタム、テレフタル酸又はトリレンジアミンの製造施設のうち、蒸留施設
ヘ アルキルベンゼン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設
ト イソプロピルアルコール製造施設のうち、蒸留施設及び硫酸濃縮施設
チ エチレンオキサイド又はエチレングリコールの製造施設のうち、蒸留施設及び濃縮施設
リ 二―エチルヘキシルアルコール又はイソブチルアルコールの製造施設のうち、縮合反応施設及び蒸留施設
ヌ シクロヘキサノン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設
ル トリレンジイソシアネート又は無水フタル酸の製造施設のうち、ガス冷却洗浄施設
ヲ ノルマルパラフイン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設及びメチルアルコール蒸留施設
ワ プロピレンオキサイド又はプロピレングリコールのけん化器
カ メチルエチルケトン製造施設のうち、水蒸気凝縮施設
ヨ メチルメタアクリレートモノマー製造施設のうち、反応施設及びメチルアルコール回収施設
タ 廃ガス洗浄施設
三十八 石けん製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 原料精製施設
ロ 塩析施設
三十八の二 界面活性剤製造業の用に供する反応施設(一・四―ジオキサンが発生するものに限り、洗浄装置を有しないものを除く。)
三十九 硬化油製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 脱酸施設
ロ 脱臭施設
四十 脂肪酸製造業の用に供する蒸留施設
四十一 香料製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 洗浄施設
ロ 抽出施設
四十二 ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 原料処理施設
ロ 石灰づけ施設
ハ 洗浄施設
四十三 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設
四十四 天然樹脂製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 原料処理施設
ロ 脱水施設
四十五 木材化学工業の用に供するフルフラール蒸留施設
四十六 第二十八号から前号までに掲げる事業以外の有機化学工業製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 水洗施設
ロ ろ過施設
ハ ヒドラジン製造施設のうち、濃縮施設
ニ 廃ガス洗浄施設
四十七 医薬品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 動物原料処理施設
ロ ろ過施設
ハ 分離施設
ニ 混合施設(第二条各号に掲げる物質を含有する物を混合するものに限る。以下同じ。)
ホ 廃ガス洗浄施設
四十八 火薬製造業の用に供する洗浄施設
四十九 農薬製造業の用に供する混合施設
五十 第二条各号に掲げる物質を含有する試薬の製造業の用に供する試薬製造施設
五十一 石油精製業(潤滑油再生業を含む。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 脱塩施設
ロ 原油常圧蒸留施設
ハ 脱硫施設
ニ 揮発油、灯油又は軽油の洗浄施設
ホ 潤滑油洗浄施設
五十一の二 自動車用タイヤ若しくは自動車用チユーブの製造業、ゴムホース製造業、工業用ゴム製品製造業(防振ゴム製造業を除く。)、更生タイヤ製造業又はゴム板製造業の用に供する直接加硫施設
五十一の三 医療用若しくは衛生用のゴム製品製造業、ゴム手袋製造業、糸ゴム製造業又はゴムバンド製造業の用に供するラテツクス成形型洗浄施設
五十二 皮革製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 洗浄施設
ロ 石灰づけ施設
ハ タンニンづけ施設
ニ クロム浴施設
ホ 染色施設
五十三 ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 研摩洗浄施設
ロ 廃ガス洗浄施設
五十四 セメント製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 抄造施設
ロ 成型機
ハ 水養生施設(蒸気養生施設を含む。)
五十五 生コンクリート製造業の用に供するバツチヤープラント
五十六 有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設
五十七 人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設
五十八 窯業原料(うわ薬原料を含む。)の精製業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 水洗式破砕施設
ロ 水洗式分別施設
ハ 酸処理施設
ニ 脱水施設
五十九 砕石業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 水洗式破砕施設
ロ 水洗式分別施設
六十 砂利採取業の用に供する水洗式分別施設
六十一 鉄鋼業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ タール及びガス液分離施設
ロ ガス冷却洗浄施設
ハ 圧延施設
ニ 焼入れ施設
ホ 湿式集じん施設
六十二 非鉄金属製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 還元そう
ロ 電解施設(溶融塩電解施設を除く。)
ハ 焼入れ施設
ニ 水銀精製施設
ホ 廃ガス洗浄施設
ヘ 湿式集じん施設
六十三 金属製品製造業又は機械器具製造業(武器製造業を含む。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 焼入れ施設
ロ 電解式洗浄施設
ハ カドミウム電極又は鉛電極の化成施設
ニ 水銀精製施設
ホ 廃ガス洗浄施設
六十三の二 空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設
六十三の三 石炭を燃料とする火力発電施設のうち、廃ガス洗浄施設
六十四 ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ タール及びガス液分離施設
ロ ガス冷却洗浄施設(脱硫化水素施設を含む。)
六十四の二 水道施設(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項に規定するものをいう。)、工業用水道施設(工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第六項に規定するものをいう。)又は自家用工業用水道(同法第二十一条第一項に規定するものをいう。)の施設のうち、浄水施設であつて、次に掲げるもの(これらの浄水能力が一日当たり一万立方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
イ 沈でん施設
ロ ろ過施設
六十五 酸又はアルカリによる表面処理施設
六十六 電気めつき施設
六十六の二 エチレンオキサイド又は一・四―ジオキサンの混合施設(前各号に該当するものを除く。)
六十六の三 旅館業(旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定するもの(住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第二条第三項に規定する住宅宿泊事業に該当するもの及び旅館業法第二条第四項に規定する下宿営業を除く。)をいう。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ ちゆう房施設
ロ 洗濯施設
ハ 入浴施設
六十六の四 共同調理場(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第六条に規定する施設をいう。以下同じ。)に設置されるちゆう房施設(業務の用に供する部分の総床面積(以下単に「総床面積」という。)が五〇〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
六十六の五 弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゆう房施設(総床面積が三六〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
六十六の六 飲食店(次号及び第六十六号の八に掲げるものを除く。)に設置されるちゆう房施設(総床面積が四二〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
六十六の七 そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店その他の通常主食と認められる食事を提供しない飲食店(次号に掲げるものを除く。)に設置されるちゆう房施設(総床面積が六三〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
六十六の八 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する飲食店で設備を設けて客の接待をし、又は客にダンスをさせるものに設置されるちゆう房施設(総床面積が一、五〇〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
六十七 洗濯業の用に供する洗浄施設
六十八 写真現像業の用に供する自動式フイルム現像洗浄施設
六十八の二 病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定するものをいう。以下同じ。)で病床数が三〇〇以上であるものに設置される施設であつて、次に掲げるもの
イ ちゆう房施設
ロ 洗浄施設
ハ 入浴施設
六十九 と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設
六十九の二 卸売市場(卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第二条第二項に規定するものをいう。以下同じ。)(主として漁業者又は水産業協同組合から出荷される水産物の卸売のためその水産物の陸揚地において開設される卸売市場で、その水産物を主として他の卸売市場に出荷する者、水産加工業を営む者に卸売する者又は水産加工業を営む者に対し卸売するためのものを除く。)に設置される施設であつて、次に掲げるもの(水産物に係るものに限り、これらの総面積が一、〇〇〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
イ 卸売場
ロ 仲卸売場
七十 廃油処理施設(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十四号に規定するものをいう。)
七十の二 自動車特定整備事業(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七十七条に規定するものをいう。以下同じ。)の用に供する洗車施設(屋内作業場の総面積が八〇〇平方メートル未満の事業場に係るもの及び次号に掲げるものを除く。)
七十一 自動式車両洗浄施設
七十一の二 科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関する研究、試験、検査又は専門教育を行う事業場で環境省令で定めるものに設置されるそれらの業務の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 洗浄施設
ロ 焼入れ施設
七十一の三 一般廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定するものをいう。)である焼却施設
七十一の四 産業廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項に規定するものをいう。)のうち、次に掲げるもの
イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第七条第一号、第三号から第六号まで、第八号又は第十一号に掲げる施設であつて、国若しくは地方公共団体又は産業廃棄物処理業者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第四項に規定する産業廃棄物の処分を業として行う者(同法第十四条第六項ただし書の規定により同項本文の許可を受けることを要しない者及び同法第十四条の四第六項ただし書の規定により同項本文の許可を受けることを要しない者を除く。)をいう。)が設置するもの
ロ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七条第十二号から第十三号までに掲げる施設
七十一の五 トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンによる洗浄施設(前各号に該当するものを除く。)
七十一の六 トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンの蒸留施設(前各号に該当するものを除く。)
七十二 し尿処理施設(建築基準法施行令第三十二条第一項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が五〇〇人以下のし尿浄化槽を除く。)
七十三 下水道終末処理施設
七十四 特定事業場から排出される水(公共用水域に排出されるものを除く。)の処理施設(前二号に掲げるものを除く。)
e-gov 水質汚濁防止法施行令
特定施設の解釈
さて、特定施設の理解を深めるため、改めて法律を見てみましょう。
法第2条第2項(特定施設の定義)にある以下の用語について解説します。
水質汚濁防止法 第2条(抜粋)
2 この法律において「特定施設」とは、次の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。
※なお本記事では、環境省が過去に作成していた「特定施設の解釈にかかるガイドライン」(現在はWeb上で非公開)も一部参考としています。現在この資料は、国立国会図書館などの公的機関で閲覧可能とされています。
「汚水又は廃液」
条文にある「汚水又は廃液」とは、具体的に何を指すのでしょうか。これは、条文の1,2号にあるとおり、以下の物質を含む液体のことです。
・有害物質
・生活環境に係る被害を生ずる物質
(水質汚濁防止法施行令第2条、第3条に規定さています)
物質の濃度の規定はありません。そもそも含まれる可能性が高い施設が、特定施設として規定されていると思います。
ちなみに、ドロッとした泥状のものであっても「汚水又は液体」と考えた方がいいでしょう(※)。なぜなら、汚水や廃液の含水率の規定はないからです。性状によっては汚水や廃液とみなされるケースがあります。
例えば、クリーニング店で使うドライクリーニング機。汚水を蒸発させて汚泥を回収処分(産廃として業者処分)する施設は、特定施設に該当します(過去の環境省の見解より)。
※ 明確な規定があるわけではありません。
「排出する」
「排出する」とは、施設自体から(汚水や廃液が)出るといった意味で、施設の外に出ることがあるかどうかです。外に出る頻度は特に規定はありません。
例えば、クローズドタイプのように汚水や廃液が系外に一切排出されなければ、特定施設に該当しないケースもあります(※)。しかし、年に数回だとしても、定期的に系外に排出するということであれば「排出する」とみなし、特定施設に該当する可能性があります。
なお、別に定義されている「排出水」とは異なり、公共用水域に排出するもののみに限られていません。
※ こちらも明確な規定がないため、解釈は自治体判断になります。
※ 「排出水」については、こちらの記事をご覧ください。
「施設」
そもそも「施設」とは何でしょう?明確な規定はありませんが、過去の環境省から疑義照会によれば、
・工場・事業場に一定期間設置されるもの
・常時移動させながら使用するものは非該当
という考えが一般的です。
しかし、例え施設に該当しないようなバケツやドラム缶などであっても、一連の工程の中で使用するために、一定期間、一定の場所に設けられる場合は、「施設」に該当しますので要注意です。
「政令」
「政令」とは水質汚濁防止法施行令のことです。内閣が定めたもので「法律」の規定をより細かく定めたものです。
【法律】国会が定めたもの(例 水質汚濁防止法)
【政令】内閣が定めたもの(例 水質汚濁防止法施行令)
【省令】各省大臣が定めたもの(例 水質汚濁防止法施行規則)
法律⇒政令⇒省令に行くにつれて、内容が細かくなっていきます。なお、罰則は法律のみに規定。
他に【告示】【通達】【通知】などあり、より細かいことが規定されています。
環境省のサイトにこれら規定が掲載されていますので、必ず押さえておいてください。
通知などは、かなりの数がありますが、自社に関係する通知は把握しておく必要があるでしょう。
「知らなかった」じゃ済まされないのが、法律のこわいところ。
とはいえ、すべての通知を理解するのは至難の業なので、行政機関の担当者と連携を図りましょう。
特定施設の届出
特定施設を設置している場合(またはこれから設置する場合)には、こんな届出義務があります。
・特定施設設置届出
・構造等変更届出
・使用届出
・氏名等変更届出
・使用廃止届出
・承継届出
上記のうち、上の2つ(水色の下線)は60日前までに届出が必要です。他は事後30日以内に必要です。
【参考】法第5条、6条、7条、10条、11条
有害物質使用特定施設
有害物質を「製造・使用・処理」する特定施設を「有害物質使用特定施設」とよびます。通常の特定施設にかかる規制に加え、構造基準等の規制がかかります。
【参考】法第2条第8項
下水道法の特定施設との違い
下水道法にも「特定施設」が規定されていますが、水質汚濁防止法の特定施設と同じになります。
工場排水の放流先が、公共用水域の場合は水質汚濁防止法、公共下水道の場合は下水道法の適用となります。
なお、下水道法の特定施設には、水質汚濁防止法の特定施設のほかに、ダイオキシン類対策特別措置法に規定する水質基準対象施設も含まれます。
【参考】下水道法
指定施設との違い
水質汚濁防止法に「指定施設」というものが定義されています。これは「指定物質」を製造・貯蔵・使用・処理する施設と有害物質を貯蔵・使用する施設のことをいいます(有害物質を「特定施設で使用」する場合は、有害物質使用特定施設)。
【参考】第2条第4項
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
特定施設の該当性の判断
これから設置しようとする施設が、特定施設に該当するか判断する方法を解説します。参考にしてみてください。
政令に定めてあるか?
原則として、シンプルにこれだけです。
「政令に定めてあるか?」
例外的な考え方があるにせよ、定めてあれば「該当」、なければ「該当しない」。なお、政令とは水質汚濁防止法施行令(別表第1)のことです。
業種と施設の種類は?
政令には、多くの特定施設に「業種」と「施設の種類」が規定されています。
よって、自社(事業場)の業種を確認した上で、どんな施設を設置する予定か確認してください。
ちなみに業種は、会社全体ではなく、工場単位が基本です。 複数の業種が該当するケースもあります。なお、原則として、「日本標準産業分類」の業種で判断します。
※さらに詳しく知りたい方は、国の通知をご覧ください。
「水質汚濁防止法第二条第二項の特定施設について(昭和47年05月08日 環水管22号)」
迷ったら悩まず行政へ
判断に迷う場合は、自己判断せずに、事前に自治体に相談してください。
特定施設に該当する場合、施設設置の際に事前の届出義務があります。未届出は「違法」で「罰則」の対象です。
一方、特定施設に該当するかわからないけど、とりあえず届出しておけばいいとも一概に言えません。
仮に特定施設かグレーな場合でも、自治体側は届出されれば、基本的に受理すると思います。届出の段階では、施設の詳細はわからないわけですから。ただ事業者側にとっては、届出した以上、法の規制対象となって負担がかかるので、該当性はきちんと判断しておく必要があるのです。
なお、行政機関に相談する場合は、相手側の担当者名や相談日時、該当有無の判断理由を記録しておくことをおすすめします。
何年か経過して「言った言わない」は、トラブルの原因になります。行政機関担当者は、2、3年で入れ替わることが多く、担当者の個人的な見解で「届出不要」と認識していたものが、担当者が代わり、後任の方が別の見解で「届出必要」となれば、法的に届出義務のある企業側の責任になり兼ねません。
自治体によって見解が異なる?【筆者のつぶやき】
水質汚濁防止法の事務は各都道府県知事または政令市長に権限がありますが、「法律」と「実際の現場」には必ずギャップが存在します。
法律に明記されていないケースが多々あり、環境省に見解を聞いても「個別具体的に自治体で判断してください」となることもあるため、「どう判断するか?」「どう解釈するか?」は各自治体によって見解が分かれることが起こってしまうのです。
もちろん自治体にも説明責任はあるので、判断や解釈にあたっては、他事例と整合性を図ったり、国や他自治体に照会したりしながら、慎重に判断しているはずです。
特定施設の届出の具体的な書き方については、こちらの記事をご覧ください。
第5条第1項の特定施設の届出書について、わかりやすく解説!
特定施設の事例紹介
代表的な特定施設について、ご紹介します。中には「えっ!?これも??」という特定施設もあるはず。また、都道府県条例の特定施設について解説します。
代表的な特定施設
【旅館業】全国で一番多い特定施設
六十六の三 旅館業(旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定するもの(住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第二条第三項に規定する住宅宿泊事業に該当するもの及び旅館業法第二条第四項に規定する下宿営業を除く。)をいう。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ ちゆう房施設
ロ 洗濯施設
ハ 入浴施設
「令和元年度水質汚濁防止法等の施行状況(令和3年1月)」によると、この業種の特定事業場の数が、全国で1番多いようです。
ホテルや旅館、宿泊できるゴルフ場などにある、台所などのシンク、洗濯機、お風呂が相当します。
【自動式車両洗浄施設】ガソリンスタンドなどの洗車機
七十一 自動式車両洗浄施設
これが全国2位の施設です。特に業種が指定されていませんので、「全業種」が対象です。
ガソリンスタンドに限らず、自動車整備工場などで見かける「洗車施設」です。
【酸又はアルカリによる表面処理施設】
六十五 酸又はアルカリによる表面処理施設
これは全国9位の施設ですが、こちらも特に業種が指定されておらず、表面処理をする施設を持つ事業者が対象になります。
なお、有害物質を使用し「有害物質使用特定施設」に該当するケースが多いので、要注意です。
【科学技術の用に供する洗浄施設】実験室の流し台など
七十一の二 科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関する研究、試験、検査又は専門教育を行う事業場で環境省令で定めるものに設置されるそれらの業務の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 洗浄施設
ロ 焼入れ施設
これは全国10位の施設ですが、わりと「これが特定施設なの!?」と思うような施設ではないでしょうか?
ここでいう「イ 洗浄施設」の例としては、研究や検査などで器具を洗浄したりするのに使う「流し台」のことです。
「環境省令で定めるもの」とは以下のとおりです。
・国又は地方公共団体の試験研究機関(人文科学のみに係るものを除く。)
・大学及びその附属試験研究機関(人文科学のみに係るものを除く。)
・学術研究(人文科学のみに係るものを除く。)又は製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究を行う研究所(前2号に該当するものを除く。)
・農業、水産又は工業に関する学科を含む専門教育を行う高等学校高等専門学校、専修学校、各種学校、職員訓練施設又は<職業訓練施設
・保健所
・検疫所
・動物検疫所
・植物検疫所
・家畜保健衝生所
・検査業に属する事業場
・商品検査業に属する事業場
・臨床検査業に属する事業場
・犯罪鑑識施設
つまり、官公庁や民間であるかを問わず、該当する場合はすべてです。もちろん工業高校や農業高校の実験室にある「流し台」も対象なので要注意です。
【し尿処理施設】大きな浄化槽
七十二 し尿処理施設(建築基準法施行令第三十二条第一項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が五〇〇人以下のし尿浄化槽を除く。)
一般家庭に設置されているような5~10人槽規模の浄化槽は、特定施設には該当しません。しかし501人槽以上の浄化槽(し尿処理施設)を設置する場合は、水質汚濁防止法の特定施設に該当します。
なお、指定地域の場合、指定地域特定施設(201人~500人槽)があります。
都道府県条例による特定施設(横出し規制)
水質汚濁防止法の特定施設に該当しない場合でも、各自治体が独自に定める「都道府県条例」により「特定施設」を定めていることがあります(これを通称「横出し」規制といいます)。
ただし、条例に定める特定施設があっても、水質汚濁防止法の届出をしていれば、免除されるケースもありますので、必ず自社工場のある自治体の条例を確認してください。
担当者が確認すべきポイント

まず自社の届出を確認してください
この記事をご覧の方は、おそらく自社の工場・事業場に特定施設があると思います。過去に行政に提出した届出の控えを見てください。

見つかりましたか?
過去に特定施設を設置した際や、何か変更があった場合、行政機関に届出義務があるので、行政機関の押印がある控えの「特定施設設置届出書」があるはずです。
そしたら、一番最初のページのここ(黄色い部分)を確認してください。

「特定施設の種類」が何か分かったと思います。特定施設を複数設置している場合など、他にも届出をしていないか確認し、自社の特定施設は何か必ず「すべて」把握してください。
届出が見つからない場合はどうすればいいか
その時は、仕方がないので、所管する自治体(役所)にご相談ください。
ただし、自社の届出であっても、閲覧するには(場合によっては届出の有無を聞きたいだけでも)「情報公開請求」の手続きが必要になることもあります。
ちなみに、所管する自治体は、工場、事業場がある場所によって異なります。
基本的には、「都道府県」(通常はその出先機関)になりますが、政令指定都市などの大きな都市の場合は「市」になります。
不明な場合は、とりあえず、工場、事業場のある都道府県庁または市町村役場にご相談ください。
現状と届出内容が変わっていないか?
届出を確認したら、現状と届出内容が変わっていないかチェックしてください。
特定施設に限定すれば、以下のとおりです。
1.種類、設置数
2.構造(能力、設置場所など)
3.使用の方法(使用時間、使用する原料、汚水の状態など)
4.有害物質の使用状況
まずは現場に届出持っていき、届出に添付した図面などと変更がないか確認してください。
特定施設以外にも、
・「届出者」(会社の代表)
・「汚水等の処理の方法」
・「排出水の汚染状態及び量」など
他にも届出内容と現状が変わっていないか、届出漏れがないか確認してください。
未届出の場合はどうすればいいか
万が一、届出の記載事項と現状が変わっているのにも関わらず、届出期間を過ぎていた場合、法的にはアウトです。至急、自治体に連絡し、速やかに届出してください。
未届は違法で罰則規定があります。
ただ、全国的に未届の違反件数は0件であり(令和元年度施行状況調査より)、速やかに届出し、生活環境に影響を及ぼしていないことが確認されれば、顛末書の提出や口頭指導で済む可能性もあります(自治体の判断によります)。
ただし、最悪なのは、基準を満たさない特定施設などをすでに設置してしまった場合です。その場合は、改善されるまで施設を使用できなくなるおそれがあります。
今後、届出内容を変更する予定はあるか?
新たに特定施設を設置する場合や、特定施設の構造や使用の方法を変更する場合は、60日前までに届出しなければなりません。
具体的には、「設置しようとするとき」「変更しようとするとき」であり、通常は、機械・設備的なものであれば「据付工事着手時」、建築・建設的なものであれば「基礎工事着手時」になります。
施設の設置工事などを予定している場合は、必ず事前に届出のスケジュールも確認しておいてください。届出のせいで、工事が遅れたら、事業に支障をきたしますしね。
特定施設の届出の具体的な書き方については、こちらの記事をご覧ください。
第5条第1項の特定施設の届出書について、わかりやすく解説!
まとめ
・特定施設とは、汚水や廃液を排出する施設であり、政令に規定してあるもの
・特定施設に該当するかは、基本的には、政令に規定してあるかどうかで判断
・届出担当者は、まずは自社の届出を確認し、現状と変わっていないか確認する
・今後、特定施設を新たに設置又は変更する場合は、届出スケジュールを確認する
水質汚濁防止法の特定施設が、どういうものかご理解いただけたでしょうか。特定施設とは何か、法のどこに規定されているのか、該当性の判断はどうすればいいのか、おわかりいただけたかと思います。
社内で情報共有しながら、水質汚濁防止法の適切な運用に努めていただければ幸いです。
水質汚濁防止法のおススメの本は、こちらの記事が参考になります。
水質汚濁防止法の効果的な学習方法は、こちらの記事が参考になります。

最後までご覧いただきありがとうございました。