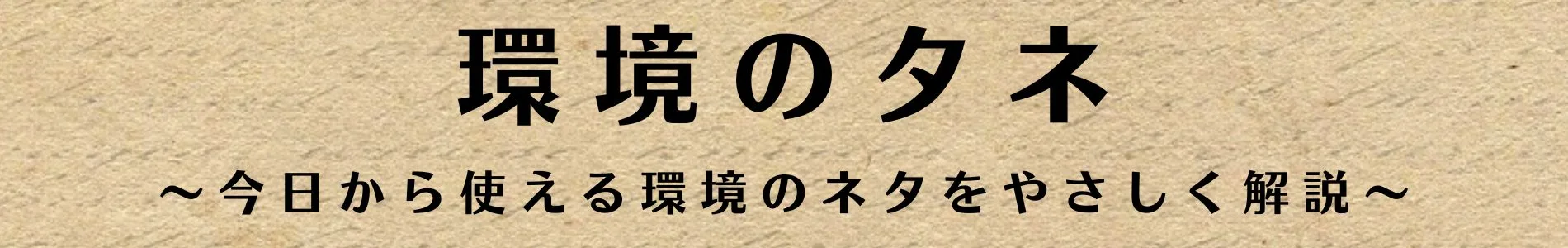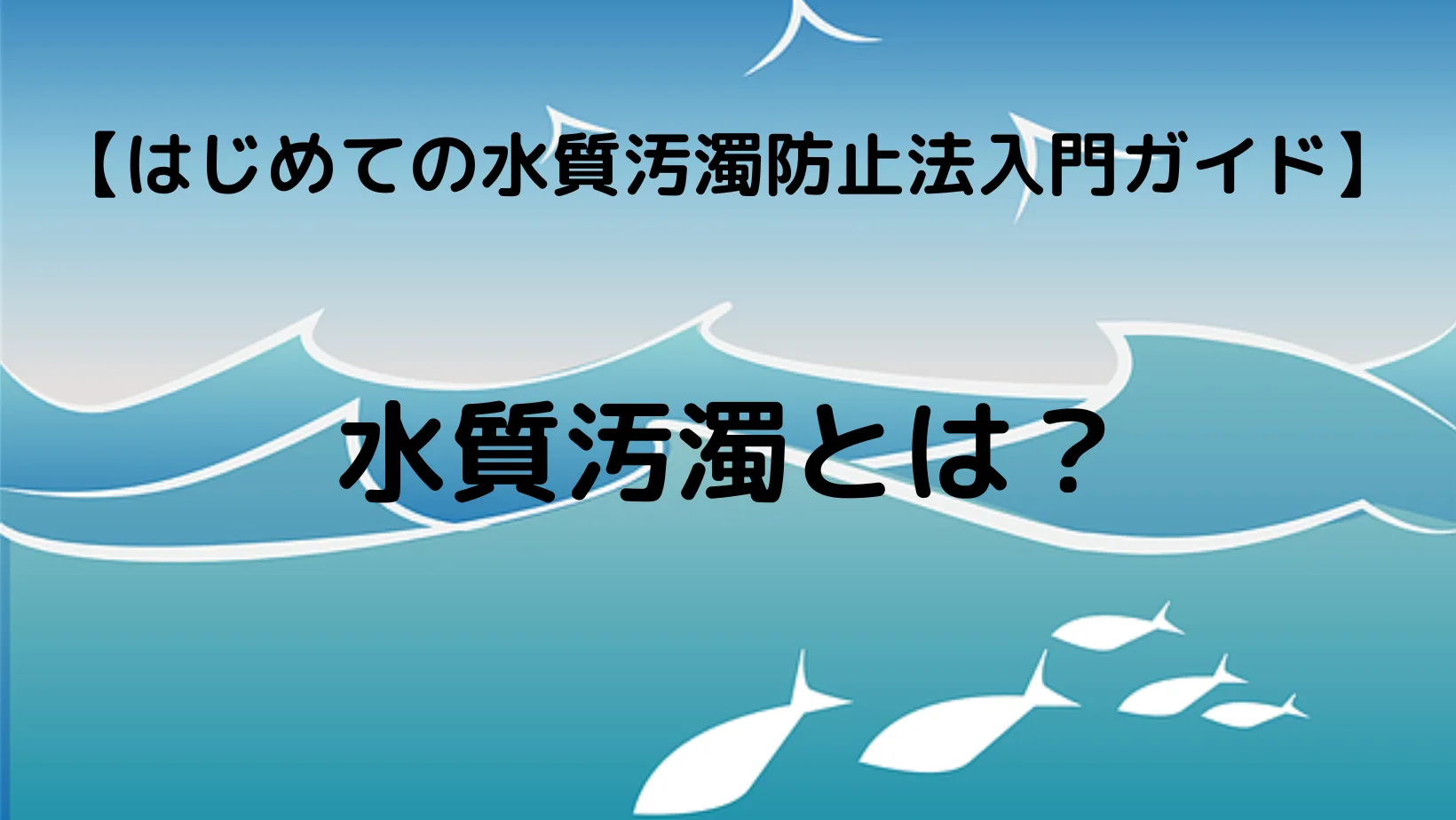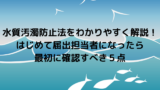本記事は「水質汚濁」をテーマに、汚濁の種類、原因、事例、汚濁を防ぐための制度についてやさしく解説します。最後に、水質汚濁について学びたい方向けのおすすめ書籍も紹介します。
※ 本ページはプロモーションが含まれています
水質汚濁とは?
「汚濁」とは、その名のとおり、“汚れて濁ること”をいい、水質汚濁とはさまざまな要因により、川や湖、海などが汚れることをいいます。
詳細は後述しますが、水質汚濁防止法という法律では、工場や事業場から出る排水の水質を規制しており、規制対象となる物質が定められています。
水質汚濁の種類
水質が汚れるといっても、その内容はさまざまです。毒性のある物質が混ざる場合もあれば、栄養分が多すぎて藻が増える場合、泥や油で見た目やにおいが悪化する場合もあります。ここでは代表的な水質汚濁の種類をわかりやすく整理します。
有害物質汚染
水銀やカドミウム、農薬や一部の化学物質など、体に害を及ぼすものが混ざるケースです。ほんの少しの量でも影響が大きいのが特徴です。
有機汚濁
食べ残しや油、紙くずなどの有機物が水に入り、分解の過程で酸素を大量に消費してしまう状態です。水がよごれてにおいや色が出やすくなります。
富栄養化現象
肥料に含まれる窒素やリンが多すぎると、藻やプランクトンが増えすぎてしまいます。湖のアオコや海の赤潮がその代表例です。魚が酸素不足で弱ることもあります。
濁水
泥や砂など細かい粒が多く含まれて水がにごる状態です。大雨や工事現場からの流入でよく見られます。
油汚染
機械油や食用油などが水に混ざり、水面に油膜ができたり強いにおいが出たりします。少量でも目立つため、漏れを防ぐ管理が大切です。
冷・温排水汚染
工場や発電所から出るお湯などで水温が変わることによる影響です。温かすぎると酸素が溶けにくくなり、生き物に負担をかけます。
酸性水
鉱山や工場から酸性の強い水が流れ出ると、水のpHが下がり魚や生き物が住みにくくなります。金属が溶け出すこともあり、中和処理が必要です。
水質汚濁の原因
水のよごれ(汚濁)は、大きく分けて自然のはたらきによるものと、人の活動によるものがあります。自然のものは一時的で回復することも多いですが、人が出す排水は量が多く、自然の力では処理しきれないことが問題になります。
自然汚濁
もともと自然の働きで起きる水のよごれです。
- 大雨で山や土砂が川に大量に流れ込む
- 落ち葉や枯れ草が分解してにおいや色が出る
自然の力で時間とともに回復することも多いですが、大きな災害の後は一時的に水がかなりよごれることもあります。
人為汚濁(人の活動によるもの)
人の生活や産業活動によって生じるよごれで、現代の水質問題の中心です。さらに原因ごとに分けられます。
- 生活排水:台所や洗濯、お風呂などから出る排水。食べ残しや油、洗剤の成分が含まれ、川や湖をよごします。
- 工業排水:工場や事業場から出る排水。薬品、金属、溶剤などが混ざり、毒性が強い場合もあります。適切な処理や管理が欠かせません。
- 鉱山排水:鉱山から流れ出る水に金属分や酸が含まれることがあります。川のpHが下がり、生き物が住みにくくなります。
- 農業排水:肥料に含まれる窒素やリン、農薬などが雨で流れ込みます。湖や海で藻やプランクトンが増えすぎ、アオコや赤潮の原因になります。
- 畜産排水:家畜のふん尿が雨水と一緒に流れ込むと、栄養分が多すぎて水質が悪化します。においや酸素不足で魚が弱ることもあります。
水質汚濁の事例
水質汚濁は昔から社会問題となってきました。ここでは代表的な事例を紹介します。
公害としての事例
- イタイイタイ病(富山県):神通川に流れ込んだ鉱山排水にカドミウムが含まれ、飲み水や農作物を通じて健康被害が出ました。骨がもろくなり激しい痛みを伴う病気として知られています。
- 水俣病(熊本県):化学工場からの排水に含まれたメチル水銀が魚や貝にたまり、それを食べた人に深刻な中毒症状が出ました。感覚障害や運動障害をもたらし、世界的に知られる公害となりました。
富栄養化の事例
- アオコの発生(湖沼):湖に生活排水や農業排水が流れ込み、窒素やリンが増えると藻が異常に増えて水面を覆います。においや水質の悪化、魚の酸欠死などを招きます。
- 赤潮(海域):海でプランクトンが異常発生し、水が赤や茶色に見える現象です。酸素不足で魚介類が死んだり、養殖業に大きな被害をもたらします。
身近な事例
- 生活排水による川のよごれ:台所や洗濯の排水が処理されずに川に流れ込むと、泡立ちや悪臭が発生し、魚がすみにくくなります。都市部や人口の多い地域では特に顕著です。
- 工場排水事故:処理設備の不具合や管理ミスで、薬品や油が川に流れ出すと、一時的に水質が悪化し、生態系に影響が出ることがあります。
水質汚濁を防ぐ制度
水質汚濁を防止する主な法律を3つご紹介します。
水質汚濁防止法
工場や事業場から出る排水を規制する法律です。排水に含まれる pH・BOD・COD・SS・有害物質(カドミウム、鉛など) に基準が定められており、これを超えないように処理しなければなりません。地域によっては上乗せ基準も設けられています。公害の発生を防ぐための基本法であり、事業者は排水処理設備の設置や維持管理を徹底することが求められています。
※「汚濁負荷量」とは(参考)
水質汚濁防止法では「汚濁負荷量」という用語が定義されています。これは、排水に含まれる汚れの濃度と排水量を掛け合わせた“よごれの総量”を示します。東京湾・伊勢湾・瀬戸内海といった指定された地域では総量規制の対象となっています。
\水質汚濁防止法について詳しく知りたい方はこちら/
下水道法
家庭や事業所からの汚水を集めて処理場に送り、きれいにしてから川や海に戻す仕組みを定める法律です。生活排水や雨水を安全に処理し、悪臭や感染症の予防、水質保全を目的としています。下水処理場では主にBODやSSの削減が行われ、最近では窒素やリンの除去も進められています。都市部の水質保全や生活環境の改善に大きく貢献してきた法律です。
浄化槽法
下水道が整備されていない地域で使われる 小規模な排水処理施設(浄化槽) について定めた法律です。トイレや生活排水を処理して水質を守る役割があり、設置や維持管理には法的な基準があります。定期的な点検・清掃・法定検査が義務付けられており、適切に管理しないと水質汚濁の原因になってしまいます。地方の水環境保全に欠かせない制度といえます。
まとめ
水質汚濁とは、水が本来持つきれいさを超えてよごれてしまうことを指します。原因には自然のものもありますが、現在の大きな問題は人の活動による排水です。
生活排水や工場排水、農業や畜産由来の水が、川や湖、海の環境に影響を与えてきました。これを防ぐために 水質汚濁防止法・下水道法・浄化槽法 が整備され、規制や管理が行われています。
水のよごれは身近でありながら社会全体に広がる課題です。基本を理解し、関心を持つことが第一歩となります。
さらに学びたい方へおすすめの書籍
水質汚濁の理解を実務につなげるうえで重要なのが、公害防止管理者という国家資格です。工場の環境管理を担う専門家であり、学習内容は水質汚濁の基礎理解にも役立ちます。ここでは、資格取得を目指す方はもちろん、「もっと体系的に学びたい」という方にもおすすめの書籍を紹介します。
『新・公害防止の技術と法規 水質編』(産業環境管理協会 編)
この本は、産業環境管理協会が作成する講習用の公式テキストであり、公害防止管理者の受験だけでなく、企業や自治体の研修教材、大学教材としても信頼されています。
『図解入門 よくわかる最新水処理技術の基本と仕組み[第3版]』(秀和システム)
この書籍は、分析化学の基本的な考え方から、代表的な分析手法(吸光光度法、電気化学分析、クロマトグラフィーなど)までを網羅した入門者向けの解説書です。
図とイラストでわかりやすく整理されており、「分析のことはよくわからない…」という方でもイメージしやすいと思います。