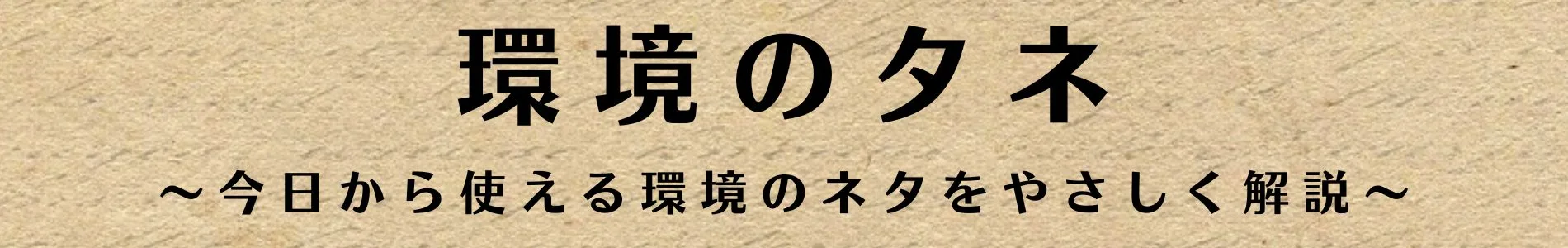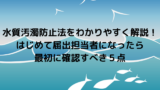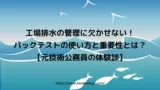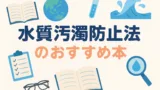工場排水や河川の水質管理において欠かせないのが、CODとBOD という2つの指標です。どちらも「水の汚れ」を示すものですが、意味や測定方法が大きく異なります。この記事では、初心者や新任担当者にも分かりやすく、CODとBODの違いと実務での使い分け方を解説します。
CODとBODの違い
CODとBODは、どちらも「有機物の汚れ」を測る指標ですが、化学的な手法と生物的な手法の違いがあります。
CODは酸化剤を用いて、水中の有機物を化学的に酸化するのに必要な酸素量を表します。これには、微生物が分解できない難分解性の有機物も含まれます。
一方、BODは微生物が分解する有機物による酸素消費量を表します。これは、自然界で微生物が有機物を分解する過程をならったものとなります。
「どちらを見ればいいのか」は、目的によって異なります。
・COD(Chemical Oxygen Demand:化学的酸素要求量)
水の中に含まれる有機物を酸化剤で分解し、そのときに必要とされる酸素量を示します。
・BOD(Biochemical Oxygen Demand:生物化学的酸素要求量)
微生物が水中の有機物を分解するときに消費される酸素量を示します。
CODとBODの値が異なることもある
CODは酸化剤によって多くの有機物を分解するのに対し、BODはあくまで微生物が分解できるもののみに限られます。そのため、COD値はBOD値よりも大きくなるのが一般的です。特に工場排水では、微生物が分解できない難分解性の有機物が含まれるため、CODの方が高く出る傾向があります。
- CODは「水中に存在する酸化されやすい物質の総量」を反映
- BODは「微生物が実際に分解できる有機物の量」を反映
CODの測定時間はBODより短い
CODの測定は酸化剤(過マンガン酸カリウムなど)を使うのに対し、BODは微生物の働きにより酸素消費量を測定するものです。このため、BODは通常5日間ほど測定に時間がかかります。
例えば、工場排水や下水処理場のモニタリングといった日常的な監視など「速報性を重視する場面」ではCOD が使われやすいです。
- COD:薬品(酸化剤)を使って化学的に有機物を分解
→ 数時間で結果が出る - BOD:水を密閉容器に入れ、微生物が酸素を消費する量を測定
→ 測定には通常5日間かかる
工場排水におけるCODとBODの基準(水質汚濁防止法)
工場や事業場からの排水に対して、水質汚濁防止法ではCODとBODの排水基準を定めています。
- 湖沼や海域以外(河川など)に排出する場合:
BOD(生物化学的酸素要求量)= 160 mg/L以下(日間平均 120mg/L) - 湖沼や海域に排出する場合:
COD(化学的酸素要求量)= 160 mg/L以下(日間平均 120mg/L)
なぜ河川と海域などで使い分けられているかというと、河川は流れがあり微生物による自然浄化が働くため「分解可能な有機物量」を示すBODが適しているのに対し、湖沼や海域は水が滞留して酸素不足が起こりやすく、酸化されやすい物質全体を評価できるCODが有効とされているからです。
なお、これらの基準値は「排水基準を定める省令」で規定されており、業種や地域によっては、より厳しい上乗せ排水基準が条例等で定められる場合があります。排水基準違反は直罰式なので十分ご留意ください。

排水基準について知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
\水質汚濁防止法について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください/
CODとBODの検査キット

CODとBODを簡単に測れる「パックテスト」をご紹介します
パックテスト BOD WAK-BOD(共立理化学研究所)
BODの正式な測定には5日かかりますが、2分間で測れるのがこちらのパックテストです。自治体や研究機関でも簡易検査のためによく使われています。
水質管理を行う場合は、必ず公定法との相関性を確認した上でご活用ください。
パックテスト COD WAK-COD-2(共立理化学研究所)
こちらも排水管理や水質の検査によく使用されるものです。5分間で0から100mg/Lの範囲のCODが測定できます。
使用する際は、説明書をよく読み、手袋着用の上で行ってください。
なお、パックテストには有効期限があるため、普段からご利用されている方も要注意です(1~2年)。
\パックテストの使い方や他の種類などについて知りたい方はこちらの記事をご覧ください/
まとめ
CODとBODは、どちらも「水の汚れ」を示す大切な指標です。
- COD=数時間で測れる、汚れの総量を把握
- BOD=5日かかる、自然界で分解可能な成分を把握
- 工場排水には、COD、BODに規制が係る場合もある
実務では、目的に応じて使い分けることが重要です。
排水処理や水質管理に携わる人にとって、この2つの違いを理解しておくことは必須といえるでしょう。
※ 本記事で解説した内容は「公害防止管理者試験」にも頻出です。資格取得を目指す方は、あわせて以下の記事もご覧ください。
さらに”水質”の理解を深めたい方へ

他の水質検査キットと水質を学ぶのに役立つ書籍を紹介します
川の水調査セット AZ-RW-3(共立理化学研究所 )
こちらは川の水の調査に役立つパックテストです。COD、アンモニウム態窒素、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素、リン酸態リンという5つの項目を測定できます。
CODに加え、窒素やリンなども川や海などの「富栄養化」の原因のひとつです。自由研究などにおもしろそうです。
『図解入門 よくわかる最新水処理技術の基本と仕組み[第3版]』(秀和システム)
水処理に関心を持たれた方向けの本です。分析化学の基本的な考え方から、代表的な分析手法(吸光光度法、電気化学分析、クロマトグラフィーなど)までを網羅した入門者向けの解説書です。
図とイラストでわかりやすく整理されており、「分析のことはよくわからない…」という方でもイメージしやすいと思います。
『新・公害防止の技術と法規 水質編』(産業環境管理協会 編)
こちらは工場排水に関わる人向けの本です。産業環境管理協会が作成する講習用の公式テキストであり、公害防止管理者の受験だけでなく、企業や自治体の研修教材、大学教材としても信頼されています。
卓上アクリル元素周期表(おまけ)
最後におまけですが、化学関連のインテリアアイテムとして、机に置いて楽しめる卓上アクリル元素周期表をご紹介します。