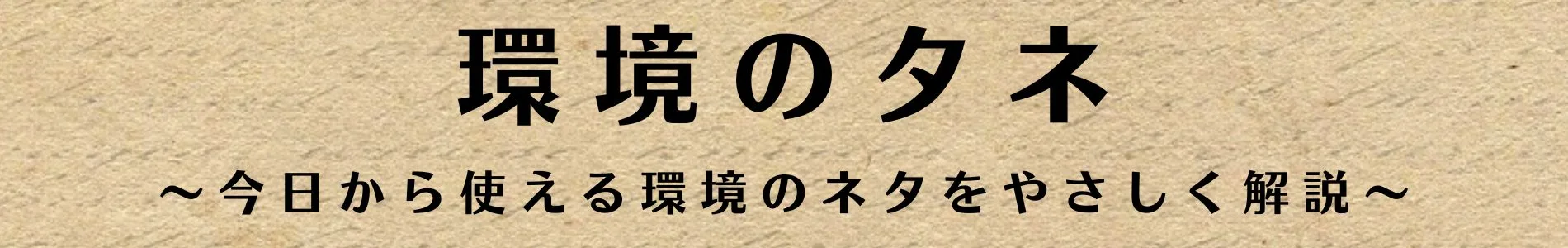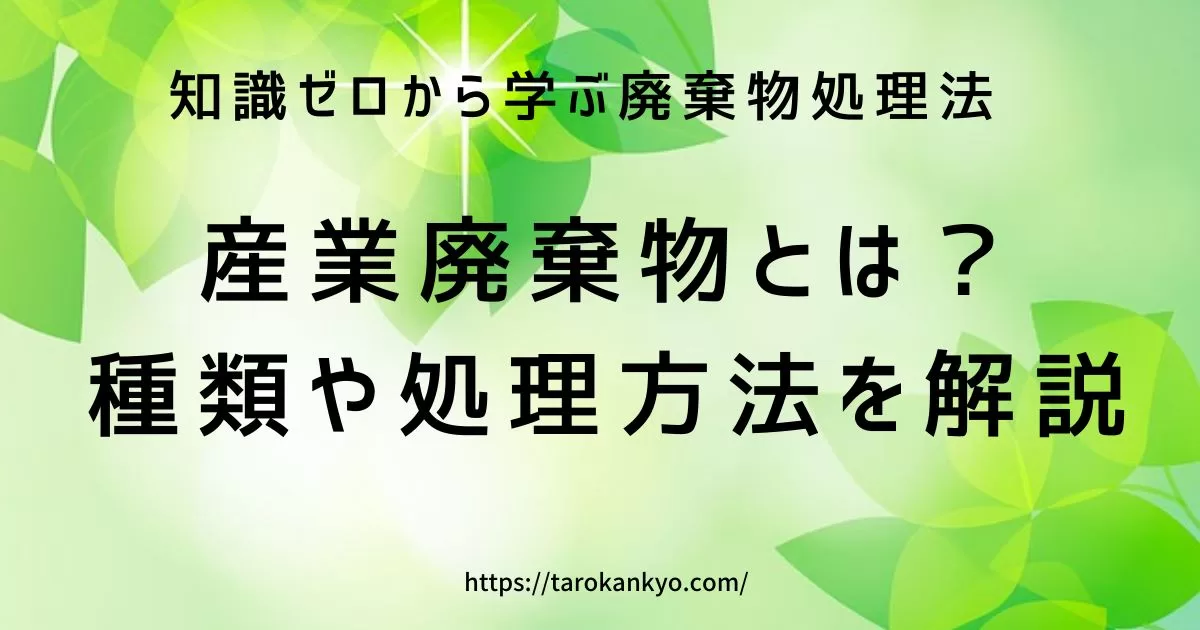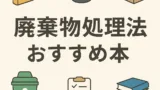そもそも「産業廃棄物」って何?会社から出るゴミのこと??

今回はこんな疑問にお答えします
例えば、こんな方におすすめです
・産業廃棄物が何かできるだけ簡単に知りたい方
・企業やお店で出るごみをどのように処分したらいいかわからない方
・法律や自治体のサイトを見てもよくわからない方
・企業で、新しく廃棄物の担当者になった方
・廃棄物処理法について知りたい方 など
産業廃棄物(産廃)をきちんと理解しておくと、こんなメリットがあるはずです。
・どれが産廃でどれが産廃じゃないか見分けられる
・法律を守ってゴミの処分ができるようになる
・コンプライアンスを徹底できる(違反は重罰)
産廃って、イメージよりもずっと複雑です。本記事では、行政で廃棄物処理法の担当をしていた私が、ポイントだけをわかりやすく解説しましたので、ぜひお役立てください。
なお、本記事は環境省や自治体の一次情報を基本としており、信頼性の確保に努めています。
・廃棄物処理法の行政担当者(元公務員技術職)
・廃棄物処理施設技術管理者の有資格者
※実際の法的な解釈は自治体の判断により分かれることがありますので、お住いの自治体にご相談ください。
※記事内で引用している法律の条文などは、法改正によって更新されている可能性もあります。出典元より、最新版をご確認ください。
産業廃棄物の概要

以下のポイントについて、順にお話しします。
・そもそも産廃って何で決まっているの?
・産廃の種類ってどれくらいあるの?
・産廃以外のゴミはどんなものがあるの?
廃棄物処理法で定義
産業廃棄物は「産廃(さんぱい)」ともよばれますが、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、通称「廃棄物処理法」または「廃掃法(ハイソウホウ)」という法律で定義されている用語です。
そこで、産業廃棄物は、このように定義されています。
・事業活動に伴って発生したもの
・燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、その他政令で定めたもの
つまり、この2つの要件にあてはまるゴミをいいます。
廃棄物処理法 第2条【抜粋】
4 この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | e-Gov法令検索
一 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
事業活動で出たゴミ
それでは「事業活動に伴って発生したゴミ」とはなんでしょうか?
社会通念上、事業活動とは、法人、個人を問わずあらゆる事業が当てはまります。つまり、会社やお店、工場、病院、農業など、あらゆる事業活動の結果に発生したゴミのことです。言い換えると、家庭から出たゴミ以外すべてとなります。
ちなみに、事業活動とは営利を伴うものに限定されていません。学校や官公庁、自治会活動によって発生するゴミもすべて当てはまります。
※「事業活動」は法で定義されていませんので、最終的な解釈は自治体判断になります。
※地震など災害によって発生したゴミは通常一般廃棄物に該当します。
「政令で定めたもの」とは?
先ほどの法第2条に「その他政令で定めたもの」とありました。
政令とは、廃棄物処理法施行令のことで、この第2条に産業廃棄物の具体的な種類が規定されています。詳細は下記をご覧ください。
(産業廃棄物)
e-gov 廃棄物処理法施行令
第二条 法第二条第四項第一号の政令で定める廃棄物は、次のとおりとする。
一 紙くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。)、出版業(印刷出版を行うものに限る。)、製本業及び印刷物加工業に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだものに限る。)
二 木くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む。)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの、貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。)
三 繊維くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)に係るもの及びポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。)
四 食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物
四の二 と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第三条第二項に規定すると畜場においてとさつし、又は解体した同条第一項に規定する獣畜及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第二条第六号に規定する食鳥処理場において食鳥処理をした同条第一号に規定する食鳥に係る固形状の不要物
五 ゴムくず
六 金属くず
七 ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものを除く。)及び陶磁器くず
八 鉱さい
九 工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物
十 動物のふん尿(畜産農業に係るものに限る。)
十一 動物の死体(畜産農業に係るものに限る。)
十二 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第二項に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法第二条第二項に規定する特定施設(ダイオキシン類(同条第一項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)を発生し、及び大気中に排出するものに限る。)又は次に掲げる廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであつて、集じん施設によつて集められたもの
イ 燃え殻(事業活動に伴つて生じたものに限る。第二条の四第七号及び第十号、第三条第三号ワ並びに別表第一を除き、以下同じ。)
ロ 汚泥(事業活動に伴つて生じたものに限る。第二条の四第五号ロ(1)、第八号及び第十一号、第三条第二号ホ及び第三号ヘ並びに別表第一を除き、以下同じ。)
ハ 廃油(事業活動に伴つて生じたものに限る。第二十四条第二号ハ及び別表第五を除き、以下同じ。)
ニ 廃酸(事業活動に伴つて生じたものに限る。第二十四条第二号ハを除き、以下同じ。)
ホ 廃アルカリ(事業活動に伴つて生じたものに限る。第二十四条第二号ハを除き、以下同じ。)
ヘ 廃プラスチック類(事業活動に伴つて生じたものに限る。第二条の四第五号ロ(5)を除き、以下同じ。)
ト 前各号に掲げる廃棄物(第一号から第三号まで及び第五号から第九号までに掲げる廃棄物にあつては、事業活動に伴つて生じたものに限る。)
十三 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、前各号に掲げる廃棄物(第一号から第三号まで、第五号から第九号まで及び前号に掲げる廃棄物にあつては、事業活動に伴つて生じたものに限る。)又は法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物を処分するために処理したものであつて、これらの廃棄物に該当しないもの
産業廃棄物の種類
全20種類!業種によって異なる
政令にあるとおり、産業廃棄物は全部で20種類あります。
出典:日本産業廃棄物処理振興センターホームページ
種類 具体例 あらゆる事業活動に伴うもの (1) 燃え殻 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残さ (2) 汚泥 排水処理後および各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等 (3) 廃油 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等 (4) 廃酸 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等すべての酸性廃液 (5) 廃アルカリ 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等すべてのアルカリ性廃液 (6) 廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状・液状のすべての合成高分子系化合物 (7) ゴムくず 生ゴム、天然ゴムくず (8) 金属くず 鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等 (9) ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等 (10) 鉱さい 鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等 (11) がれき類 工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物 (12) ばいじん 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの 特定の事業活動に伴うもの (13) 紙くず 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず (14) 木くず 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材・木製品製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等
貨物の流通のために使用したパレット等(15) 繊維くず 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず (16) 動植物性残さ 食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚および獣のあら等の固形状の不要物 (17) 動物系固形不要物 と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物 (18) 動物のふん尿 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿 (19) 動物の死体 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体 (20) 以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(例えばコンクリート固型化物)
ポイントは、業種が指定されているなど特定の事業活動に限定されているものと、そうでないものがあることです。
(1) 燃え殻
(2) 汚泥
(3) 廃油
(4) 廃酸
(5) 廃アルカリ
(6) 廃プラスチック類
(7) ゴムくず
(8) 金属くず
(9) ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず
(10) 鉱さい
(11) がれき類
(12) ばいじん
(20) 産業廃棄物を処分するために処理したもので、他の産業廃棄物に該当しないもの
(13) 紙くず(建設業、製紙業など)
(14) 木くず(建設業、木材製造業など)(※注)
(15) 繊維くず(建設業など)
(16) 動植物性残さ(食料品製造業など)
(17) 動物系固形不要物(と畜場など)
(18) 動物のふん尿(畜産農業のみ)
(19) 動物の死体(畜産農業のみ)
つまり、業種が指定されている場合、該当しない業種から出たゴミは産業廃棄物にはなりません。
例)動植物性残さ(生ごみなど)
・食料品製造業から出た場合は、産業廃棄物になる
・スーパーなど小売業から出た場合は、産業廃棄物にならない(一般廃棄物)
※木くずについて、貨物の流通のために使用したパレットは、業種によらず「木くず」に該当します。
特別管理産業廃棄物とは?
産業廃棄物の中で「爆発性」「毒性」「感染性」があるものは、「特別管理産業廃棄物」(いわゆる「特管(とっかん)」)になり、産業廃棄物は別の取り扱いになるので注意が必要です。
例えば、こんなものが特管になります。
・廃油(揮発油類、灯油類など)
・廃酸、廃アルカリ(pH2.0以下またはpH12.5以上)
・感染性廃棄物(病院などから出た注射針など)
・その他
特管を取り扱う場合、「特別管理産業廃棄物管理責任者」を選任する義務があります。ここでは詳細な説明は省きますが、自治体の条例などにより、選任したら届出義務が発生するケースもあります。
特管の詳細や根拠条文は、以下をご参照ください。
種類 性状および事業例 廃油 揮発油類、灯油類、軽油類の燃えやすい廃油《事業例》紡績、新聞、香料製造、医療品製造、石油精製、電気めっき、洗濯、科学技術研究、その他 廃酸
廃アルカリpH2.0以下の酸性廃液、pH12.5以上のアルカリ性廃液《事業例》カセイソーダ製造、無機顔料製造、無機・有機化学工業製品製造、アセチレン誘導品製造、医薬・試薬・農薬製造、金属製品製造、石油化学工業製品製造、非鉄金属製造、ガラス・窯業、科学技術研究、その他 感染性産業廃棄物 感染性病原体が含まれるか、付着しているか又はそれらのおそれのある産棄廃棄物
(血液の付着した注射針、採血管等)《事業例》病院、診療所、衛生検査所、老人保健施設、その他特定有害産業廃棄物 廃PCB等 廃PCBおよびPCBを含む廃油 PCB汚染物 PCBが染み込んだ汚泥、PCBが塗布もしくは染み込んだ紙くず、PCBが染み込んだ木くず、もしくは繊維くず、またはPCBが付着もしくは封入された廃ブラスチック類や金属くず、PCBが付着した陶磁器くずやがれき類 PCB処理物 廃PCB等またはPCB汚染物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る) 廃水銀等
及びその処理物・廃水銀等(廃水銀及び廃水銀化合物)
・廃水銀等を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る)《事業例》水銀回収施設、水銀使用製品製造施設、水銀を媒体とする測定機器を有する施設、大学及びその附属試験研究機関、その他廃石綿等 建築物その他の工作物から除去した飛散性の吹付け石綿、石綿含有保温材、断熱材、耐火被覆材およびその除去工事から排出されるプラスチックシート等で、石綿が付着しているおそれのあるもの、大気汚染防止法の特定粉じん発生施設で生じた石綿で集じん施設で集められたもの等《事業例》石綿建材除去事業等 有害産業廃棄物 水銀、カドミウム、鉛、有機燐化合物、六価クロム、砒素、シアン、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、1,4-ジオキサン又はその化合物、ダイオキシン類が基準値を超えて含まれる汚泥、鉱さい、廃油、廃酸、廃アルカリ、燃え殻、ばいじん等《事業例》大気汚染防止法(ばい煙発生施設)、水質汚濁防止法(特定事業場)等に規定する施設・事業場 出典:日本産業廃棄物処理振興センターホームページ
(廃棄物処理法)第2条[抜粋]
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | e-Gov法令検索
5 この法律において「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。
(特別管理産業廃棄物)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 | e-Gov法令検索
第二条の四 法第二条第五項(ダイオキシン類対策特別措置法第二十四条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。
一 廃油(燃焼しにくいものとして環境省令で定めるものを除く。)
二 廃酸(著しい腐食性を有するものとして環境省令で定める基準に適合するものに限る。)
三 廃アルカリ(著しい腐食性を有するものとして環境省令で定める基準に適合するものに限る。)
四 感染性産業廃棄物(別表第一の四の項の下欄に掲げる廃棄物(法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるものに限る。)及び別表第二の下欄に掲げる廃棄物(国内において生じたものにあつては、同表の上欄に掲げる施設において生じたものに限る。)をいう。以下同じ。)
五 特定有害産業廃棄物(次に掲げる廃棄物をいう。)
イ 廃ポリ塩化ビフェニル等(廃ポリ塩化ビフェニル及びポリ塩化ビフェニルを含む廃油をいう。以下同じ。)
ロ ポリ塩化ビフェニル汚染物(次に掲げるものをいう。以下同じ。)
(1) 汚泥(事業活動に伴つて生じたもの及び法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物のうち日常生活に伴つて生じたもの(以下「事業活動等発生物」という。)に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(2) 紙くず(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだもの
(3) 木くず(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの
(4) 繊維くず(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの
(5) 廃プラスチック類(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着し、又は封入されたもの
(6) 金属くず(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着し、又は封入されたもの
(7) 陶磁器くず(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着したもの
(8) 工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着したもの
ハ ポリ塩化ビフェニル処理物(廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル汚染物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)をいう。以下同じ。)
ニ 廃水銀等(廃水銀及び廃水銀化合物であつて、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして環境省令で定めるものをいう。以下同じ。)及び当該廃水銀等を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ホ 下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第十三条の四の規定により指定された汚泥(以下「指定下水汚泥」という。)(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及び当該指定下水汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ヘ 第二条第八号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。以下「鉱さい」という。)(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及び当該鉱さいを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ト 廃石綿等(廃石綿及び石綿が含まれ、又は付着している産業廃棄物のうち、石綿建材除去事業(建築物その他の工作物に用いられる材料であつて石綿を吹き付けられ、又は含むものの除去を行う事業をいう。)に係るもの(輸入されたものを除く。)、別表第三の一の項に掲げる施設において生じたもの(輸入されたものを除く。)及び輸入されたもの(事業活動に伴つて生じたものに限る。)であつて、飛散するおそれのあるものとして環境省令で定めるものをいう。以下同じ。)
チ 第二条第十二号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限るものとし、法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたばいじんであつて集じん施設によつて集められたものを除く。次号、第七号及び第九号、第三条第三号並びに別表第一を除き、以下「ばいじん」という。)であつて次に掲げるもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及び当該ばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(1) ばいじん(国内において生じたものにあつては、別表第三の二の項に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて、水銀又はその化合物を含むもの
(2) ばいじん(国内において生じたものにあつては、別表第三の三の項に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて、一・四―ジオキサンを含むもの
リ 次に掲げるばいじん又は燃え殻(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(1) ばいじん(国内において生じたものにあつては、第七条第八号又は別表第三の四の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同号に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて、カドミウム又はその化合物を含むもの
(2) ばいじん(国内において生じたものにあつては、第七条第八号又は別表第三の五の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同号に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて、鉛又はその化合物を含むもの
(3) ばいじん(国内において生じたものにあつては、第七条第八号若しくは第十三号の二又は別表第三の六の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、これらの号に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて、六価クロム化合物を含むもの
(4) ばいじん(国内において生じたものにあつては、第七条第十三号の二又は別表第三の七の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同号に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて、砒ひ素又はその化合物を含むもの
(5) ばいじん(国内において生じたものにあつては、第七条第八号又は別表第三の八の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同号に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて、セレン又はその化合物を含むもの
(6) ばいじん(国内において生じたものにあつては、別表第三の九の項又は一〇の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたものを除き、同表の一〇の項に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて、ダイオキシン類を含むもの
ヌ 次に掲げる廃油及び当該廃油を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(1) 廃溶剤(トリクロロエチレンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一一の項に掲げる施設において生じたものに限る。)
(2) 廃溶剤(テトラクロロエチレンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一二の項に掲げる施設において生じたものに限る。)
(3) 廃溶剤(ジクロロメタンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一三の項に掲げる施設において生じたものに限る。)
(4) 廃溶剤(四塩化炭素に限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一四の項に掲げる施設において生じたものに限る。)
(5) 廃溶剤(一・二―ジクロロエタンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一五の項に掲げる施設において生じたものに限る。)
(6) 廃溶剤(一・一―ジクロロエチレンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一六の項に掲げる施設において生じたものに限る。)
(7) 廃溶剤(シス―一・二―ジクロロエチレンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一七の項に掲げる施設において生じたものに限る。)
(8) 廃溶剤(一・一・一―トリクロロエタンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一八の項に掲げる施設において生じたものに限る。)
(9) 廃溶剤(一・一・二―トリクロロエタンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一九の項に掲げる施設において生じたものに限る。)
(10) 廃溶剤(一・三―ジクロロプロペンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の二〇の項に掲げる施設において生じたものに限る。)
(11) 廃溶剤(ベンゼンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の二一の項に掲げる施設において生じたものに限る。)
(12) 廃溶剤(一・四―ジオキサンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の二二の項に掲げる施設において生じたものに限る。)
ル 次に掲げる汚泥、廃酸又は廃アルカリ(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(1) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の二三の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、水銀又はその化合物を含むもの
(2) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の二四の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、カドミウム又はその化合物を含むもの
(3) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の二五の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、鉛又はその化合物を含むもの
(4) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の二六の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、有機燐りん化合物を含むもの
(5) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の二七の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、六価クロム化合物を含むもの
(6) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の二八の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、砒ひ素又はその化合物を含むもの
(7) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の二九の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、シアン化合物を含むもの
(8) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三〇の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、ポリ塩化ビフェニルを含むもの
(9) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三一の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、トリクロロエチレンを含むもの
(10) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三二の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、テトラクロロエチレンを含むもの
(11) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三三の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、ジクロロメタンを含むもの
(12) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三四の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、四塩化炭素を含むもの
(13) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三五の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、一・二―ジクロロエタンを含むもの
(14) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三六の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、一・一―ジクロロエチレンを含むもの
(15) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三七の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、シス―一・二―ジクロロエチレンを含むもの
(16) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三八の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、一・一・一―トリクロロエタンを含むもの
(17) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三九の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、一・一・二―トリクロロエタンを含むもの
(18) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の四〇の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、一・三―ジクロロプロペンを含むもの
(19) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の四一の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、テトラメチルチウラムジスルフィド(以下「チウラム」という。)を含むもの
(20) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の四二の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、二―クロロ―四・六―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(以下「シマジン」という。)を含むもの
(21) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の四三の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、S―四―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(以下「チオベンカルブ」という。)を含むもの
(22) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の四四の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、ベンゼンを含むもの
(23) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の四五の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、セレン又はその化合物を含むもの
(24) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の四六の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、一・四―ジオキサンを含むもの
(25) 汚泥(法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたものを除く。)、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の四七の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、ダイオキシン類を含むもの
六 法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却施設(一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上又は火格子面積(火格子の水平投影面積をいう。以下同じ。)が二平方メートル以上の焼却施設であつて、環境省令で定めるものに限る。)において発生するばいじんであつて集じん施設によつて集められたもの及び当該ばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
七 別表第三の一〇の項に掲げる施設において法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたばいじん(集じん施設によつて集められたものに限るものとし、前号に掲げるものを除く。)又は燃え殻(これらに含まれるダイオキシン類の量がダイオキシン類対策特別措置法第二十四条第一項の環境省令で定める基準を超えるものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
八 別表第三の一〇の項に掲げる施設において法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じた汚泥(ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)別表第二第十五号に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)であつてダイオキシン類を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及び当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
九 ばいじん(集じん施設によつて集められたものであつて、法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるものに限る。)
十 燃え殻(法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるものに限る。)であつてダイオキシン類を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
十一 汚泥(法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるものに限る。)であつてダイオキシン類を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
産業廃棄物以外はすべて一般廃棄物
では、上記の産業廃棄物(特別産業廃棄物)に該当しないゴミは、どうなるのでしょうか。
それらはすべて一般廃棄物になります。
つまり、会社やお店などから出るゴミでも、一般廃棄物になるのです。よく家庭ごみを区別するのに、「事業系一般廃棄物」とよばれることもあります。もちろん、家庭ごみとは違うので、近所のゴミステーションには廃棄できません。
なお、一般廃棄物の処理は市町村に責任があります。処理する場合、市町村の清掃工場か、市町村から許可を得た一般廃棄物処理業者(産業廃棄物処理業者とは別です)に委託してください。
産業廃棄物の処理方法

どんなゴミが産業廃棄物に該当するかわかったところで、「どうやって処分すればいいか?」について解説します。
そもそも産業廃棄物の処理の責任は、ゴミを出した事業者(排出事業者)になります。
ですので「廃棄物の処理業者にお願いしたら終わり!」というわけではなく、最後までちゃんと処分されるまでは、排出事業者の責任が重く付きまといます。
また「サステナブル経営」が叫ばれる昨今、廃棄物の減量や有効利用など「適正処理」に努めていただければと思います。
処理の大まかな流れは次のとおりです。
1.産業廃棄物の処理方法の検討
2.産業廃棄物の分別・保管
3.産業廃棄物の収集・運搬
4.産業廃棄物の中間処理・最終処分
廃棄物の処理方法の検討
廃棄物の種類は何か?
廃棄物が発生したら、一般廃棄物か?産業廃棄物か?、その種類は何か?量や性状はどうかなど判断します。その上で、自ら処分できる場合を除き、通常は廃棄物処理業者に委託して処分します。
産業廃棄物処理業者の選定
産業廃棄物処理業者に委託する場合、法律でさまざまな義務があるため要注意です。
まず委託しようとしている廃棄物処理業者が、都道府県などの許可を得ていなければなりません。
許可は、都道府県または市ごとに交付しています(産廃の場合は、都道府県か権限移譲されている政令市のみです)。
許可と言っても様々あり、「一般廃棄物の収集運搬業」「産業廃棄物の収集運搬業」「一般廃棄物の処分業」「産業廃棄物の処分業」「特別産業廃棄物の収集運搬業」「特別産業廃棄物の処分業」それぞれ別なものです。
・産業廃棄物
・特別管理産業廃棄物
・一般廃棄物
・収集運搬
・処分(中間処理・最終処分)
・都道府県
・市町村
さらに、例えば「産業廃棄物の収集運搬業」や「産業廃棄物の処分業」の許可をもっていても、「廃プラスチック類」「金属くず」など、取り扱える種類が決まっていますので、処分したい廃棄物の種類の許可をもっていなければ処分できません。
また、そもそも許可を出している自治体と関係なかったら意味がありません(例えば、東京都内の会社から出る産業廃棄物を運ぶためには、少なくとも東京都の許可のある処理業者である必要があります)
なお、収集運搬業の許可は「積み込み場所」と「荷下ろし場所」の自治体の許可が必要です。
※産業廃棄物処理業者の選定についてはこちらをご参照ください
産業廃棄物処理業者との委託契約
処理業者が決まったら「電話一本で、あとは任せた!」というわけにはいきません。法律で「委託基準」が定められており、違反すると重い罰則があるのです。
まずは処理業者と「書面で契約」する必要があります。また処理業者とは、主に2つあります。
・収集運搬業者
・処分業者(中間処理、最終処分)
上記の各業者とそれぞれ契約する必要があります。
つまり、収集運搬業者が中間処理業者と契約を結ぶわけではないので要注意です。
産業廃棄物の保管
廃棄物処理業者が取りに来るまで、社内で適切に保管する必要があります。法律で保管基準が定められており、きちんと分別し、周囲に飛散しないよう、悪臭などしないよう保管する必要があります。
(参考)
産業廃棄物の収集・運搬
収集運搬業者に、廃棄物を処分場まで運んでもらいます。
その際、処理業者に対して「マニフェスト(産業廃棄物管理票)」を交付しなければなりません。
紙と電子の2種類あり、紙マニフェストの場合は、7枚複写式になっており、運搬終了時、中間処理終了時、最終処分終了時に、各処理業者から返送されますので、適切に処分されたかどうか確認してください。なお5年間の保管義務があります。
産業廃棄物の中間処理・最終処分
廃棄物の処分場です。中間処理とは、最終処分に至るまで、破砕や脱水などすることです。最終処分とは、埋め立てになります。
なお、中間処理によって、リサイクルされれば埋め立て処分されずに済みますので、廃棄物の適正処理に努めましょう。
まとめ
産業廃棄物の種類や処理方法について解説しましたが、理解を深められたでしょうか?
これらはすべて「廃棄物処理法」という法律に定められているので、必ず確認してください。

最後までご覧いただきありがとうございました。