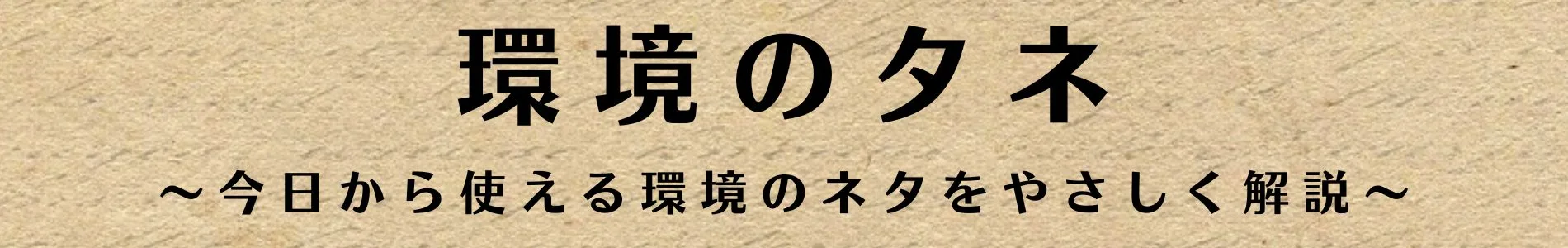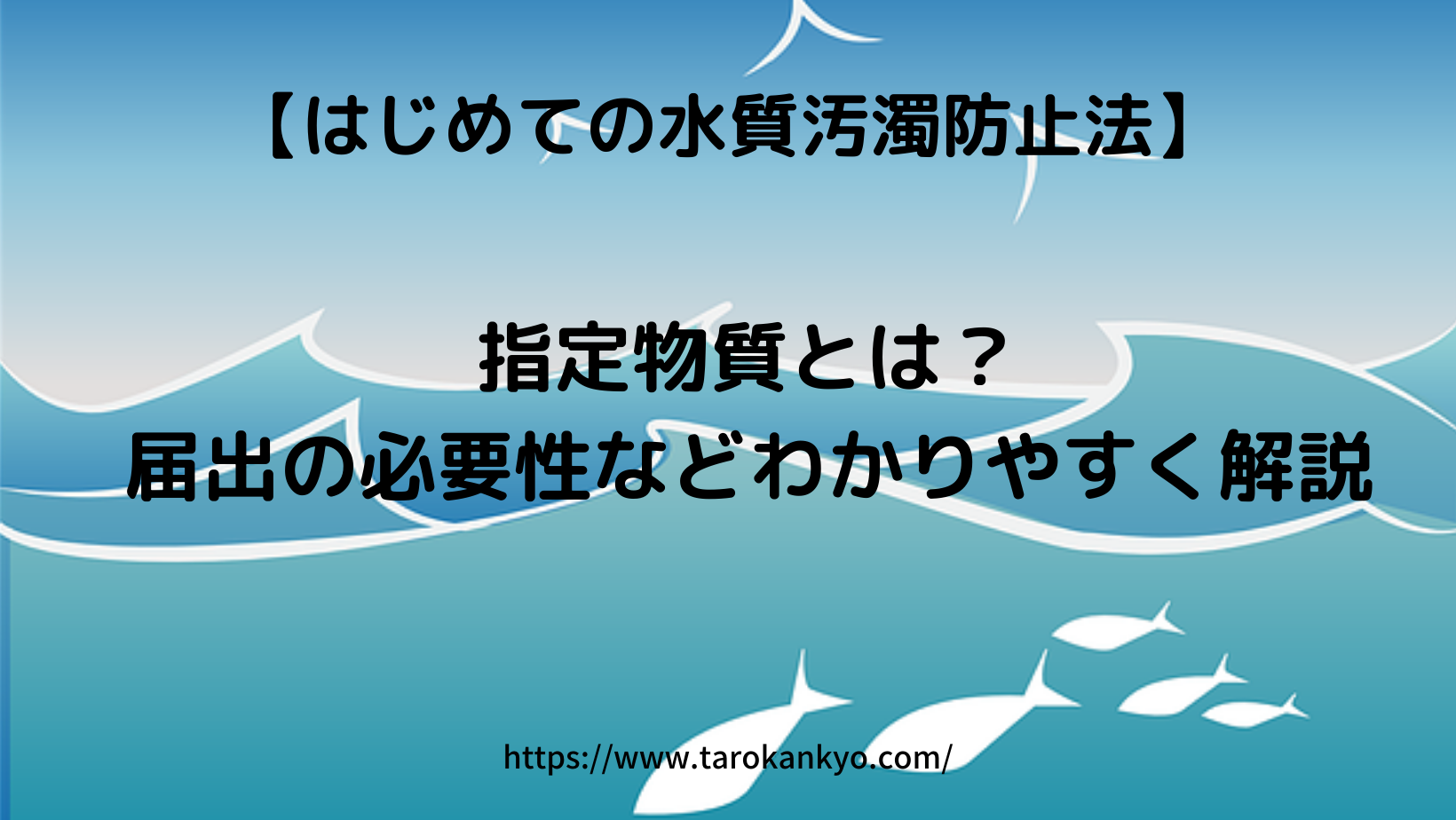水質汚濁防止法の『指定物質』ってなんだっけ?何をしなければならないの?

今回はこんな疑問にお答えします
例えば、こんな方におすすめです
・指定物質ついて理解したい
・法律や自治体のサイトを見てもよくわからない
・企業で、新しく水質汚濁防止法の届出担当者になった
・新しく特定事業場の経営者・工場長になる
・公害防止管理者を受検する予定 など
- 指定物質とは何か?
- 指定物質がある場合どうすればいいか?
水質汚濁防止法の指定物質
指定物質の定義
水質汚濁防止法第2条第4項に定義される「指定物質」とは、「有害物質や油以外の物質」で「公共用数域に多量に排出されると人の健康や生活環境に被害を及ぼすおそれがある物質」のことです。
また、指定物質を製造・貯蔵・使用・処理する施設と有害物質を貯蔵・使用する施設を「指定施設」といい、この指定施設を設置する工場または事業場を「指定事業場」といいます【法第14条の2第2項】。
水質汚濁防止法 第2条(定義)
e-gov 水質汚濁防止法
4 この法律において「指定施設」とは、有害物質を貯蔵し、若しくは使用し、又は有害物質及び次項に規定する油以外の物質であつて公共用水域に多量に排出されることにより人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定めるもの(第十四条の二第二項において「指定物質」という。)を製造し、貯蔵し、使用し、若しくは処理する施設をいう。
指定物質一覧
指定物質一覧
具体的には、水質汚濁防止法施行令第3条の3に60物質が規定されています(令和4年12月23日改正)。
| 一 ホルムアルデヒド |
| 二 ヒドラジン |
| 三 ヒドロキシルアミン |
| 四 過酸化水素 |
| 五 塩化水素 |
| 六 水酸化ナトリウム |
| 七 アクリロニトリル |
| 八 水酸化カリウム |
| 九 アクリルアミド |
| 十 アクリル酸 |
| 十一 次亜塩素酸ナトリウム |
| 十二 二硫化炭素 |
| 十三 酢酸エチル |
| 十四 メチル―ターシヤリ―ブチルエーテル(別名MTBE) |
| 十五 硫酸 |
| 十六 ホスゲン |
| 十七 一・二―ジクロロプロパン |
| 十八 クロルスルホン酸 |
| 十九 塩化チオニル |
| 二十 クロロホルム |
| 二十一 硫酸ジメチル |
| 二十二 クロルピクリン |
| 二十三 りん酸ジメチル=二・二―ジクロロビニル(別名ジクロルボス又はDDVP) |
| 二十四 ジメチルエチルスルフイニルイソプロピルチオホスフエイト(別名オキシデプロホス又はESP) |
| 二十五 トルエン |
| 二十六 エピクロロヒドリン |
| 二十七 スチレン |
| 二十八 キシレン |
| 二十九 パラ―ジクロロベンゼン |
| 三十 N―メチルカルバミン酸二―セカンダリ―ブチルフエニル(別名フエノブカルブ又はBPMC) |
| 三十一 三・五―ジクロロ―N―(一・一―ジメチル―二―プロピニル)ベンズアミド(別名プロピザミド) |
| 三十二 テトラクロロイソフタロニトリル(別名クロロタロニル又はTPN) |
| 三十三 チオりん酸O・O―ジメチル―O―(三―メチル―四―ニトロフエニル)(別名フエニトロチオン又はMEP) |
| 三十四 チオりん酸S―ベンジル―O・O―ジイソプロピル(別名イプロベンホス又はIBP) |
| 三十五 一・三―ジチオラン―二―イリデンマロン酸ジイソプロピル(別名イソプロチオラン) |
| 三十六 チオりん酸O・O―ジエチル―O―(二―イソプロピル―六―メチル―四―ピリミジニル)(別名ダイアジノン) |
| 三十七 チオりん酸O・O―ジエチル―O―(五―フエニル―三―イソオキサゾリル)(別名イソキサチオン) |
| 三十八 四―ニトロフエニル―二・四・六―トリクロロフエニルエーテル(別名クロルニトロフエン又はCNP) |
| 三十九 チオりん酸O・O―ジエチル―O―(三・五・六―トリクロロ―二―ピリジル)(別名クロルピリホス) |
| 四十 フタル酸ビス(二―エチルヘキシル) |
| 四十一 エチル=(Z)―三―[N―ベンジル―N―[[メチル(一―メチルチオエチリデンアミノオキシカルボニル)アミノ]チオ]アミノ]プロピオナート(別名アラニカルブ) |
| 四十二 一・二・四・五・六・七・八・八―オクタクロロ―二・三・三a・四・七・七a―ヘキサヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン(別名クロルデン) |
| 四十三 臭素 |
| 四十四 アルミニウム及びその化合物 |
| 四十五 ニツケル及びその化合物 |
| 四十六 モリブデン及びその化合物 |
| 四十七 アンチモン及びその化合物 |
| 四十八 塩素酸及びその塩 |
| 四十九 臭素酸及びその塩 |
| 五十 クロム及びその化合物(六価クロム化合物を除く。) |
| 五十一 マンガン及びその化合物 |
| 五十二 鉄及びその化合物 |
| 五十三 銅及びその化合物 |
| 五十四 亜鉛及びその化合物 |
| 五十五 フエノール類及びその塩類 |
| 五十六 一・三・五・七―テトラアザトリシクロ[三・三・一・一三・七]デカン(別名ヘキサメチレンテトラミン) |
| 五十七 アニリン |
| 五十八 ペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)及びその塩 |
| 五十九 ペルフルオロ(オクタン―一―スルホン酸)(別名PFOS)及びその塩 |
| 六十 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 |
PFOSとは?
指定物質にも追加されたPFOS(ピーフォス)という言葉を最近目にしませんか?これは、ペルフルオロオクタンスルホン酸という有機フッ素化合物であり、撥水性、撥油性、耐熱性や耐薬品性等で優れた性質があるため、消火薬剤など様々な分野で使用されてきました。
しかし、環境中に残留し易く、現在では環境汚染物質として注目されています。2010年のストックホルム条約を受け、日本国内においても2010年に化審法の第一種特定化学物質に指定され、2018年には全面的に製造・使用等が禁止されました。
指定物質にかかる規制
指定物質を製造・貯蔵・使用・処理する指定施設を設置している「指定事業場」に対して、「事故時の措置」の規制かかります。
「事故時の措置」とは?(第十四条の二)
施設の破損などの事故が発生し、有害物質等が河川等の公共用水域や地下に排出されたことにより、人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれがあるときには、事故時の措置、つまり「応急の措置を講じるとともに、その事故の状況等を都道府県知事等に届け出る」ことを義務付けられているものです。
(参考)環境省サイト
水質汚濁防止法(抜粋)
e-gov 水質汚濁防止法
第十四条の二 (事故時の措置)
2 指定施設を設置する工場又は事業場(以下この条において「指定事業場」という。)の設置者は、当該指定事業場において、指定施設の破損その他の事故が発生し、有害物質又は指定物質を含む水が当該指定事業場から公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く有害物質又は指定物質を含む水の排出又は浸透の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を都道府県知事に届け出なければならない。
届出義務は事故時の措置のみ
つまり、指定物質を取り扱っている場合の届出義務としては、事故が起きた場合にのみ、都道府県知事(または政令市長)に届出する必要があります。
指定物質による水質事故事例
平成24年5月に、利根川水系の浄水場の浄水過程で水道水質基準を上回るホルムアルデヒドが検出され、浄水場において取水停止が生ずる等の取水障害が発生しました。これは、廃棄物に含まれていたヘキサメチレンテトラミン(現指定物質)が十分に処理されないまま公共用水域に排出され、下流の浄水場において浄水過程で注入される塩素と反応し、ホルムアルデヒドが生成したものと強く推定されています。
(参考)環境省サイト
排水基準や構造基準の規制はない
指定物質に排水基準はありません。”多量に排出”とあるものの、基準値のような定量的な規定はありません。
しかし、例えば、硫酸や水酸化ナトリウムなどは、排水基準項目であるpHに影響を及ぼす物質です。
指定物質と有害物質の違い
指定物質と有害物質は別の物質です。油とも異なり、それぞれ政令で定められています。
| 指定物質 | 有害物質 | 油 |
| 硫酸や水酸化ナトリウムなど全60種 | カドミウムやシアンなど全28物質 | 重油、灯油など全7種 |
| 政令第3条の3 | 政令第2条 | 政令第3条の4 |
指定物質は、有害物質のように人の健康や生活環境に影響を及ぼすものではないものの、過去の事故事例や事故の起こりやすさ、人の健康被害、生活環境や水道水質への悪影響などから、選定されたものです。
担当者が確認すべきポイント
使用薬品に指定物質が含まれていないか
まずは指定物質を使用しているか確認してください。使用している薬品の成分を調べ、微量でも含まれていないか調べる必要があります。
また新たに購入した薬品などに指定物質が含まれていないかなど、普段からチェック体制も整備しておくと漏れを防げます。
さらに政令の改正により、指定物質が新たに追加されていないか、「政令を見て」確認するようにしてください。改正があっても、国や自治体から通知されてくるとは限りませんし、ホームページ上でも更新されていないこともあります。
「指定施設」はあるか、どこに設置されているのか、自社は「指定事業場」に該当するのか、設置届出や排水規制はありませんが、コンプライアンス上、理解しておく必要があります。
事故時の措置の体制は整備されているか
指定物質を使用していた場合、最も重要なのは「事故時の措置」の対応です。
平時のうちに、事故時の応急措置の方法と届出先の行政の部署の確認をしておくことをおすすめします。行政もいろいろな部署があるので、日ごろ、行政とのやり取りがない場合は、どこの部署に行けばいいか、迷ってしまうかもしれません。
届出先は都道府県庁の場合と政令指定都市や一部の中核市などの市役所のいずれかになります。
とにかく事故を起こさぬよう日常の水質検査を心がけてください。
放流先の河川の下流に浄水場はないか
過去に指定物質を流出させたことで、下流にあった浄水場に大きな被害をもたらした事故がありました。当然、周辺世帯は断水となり、原因企業は、行政から多額の賠償を強いられたようです。
危機管理の一環として、放流先の河川とその下流に浄水場がないか確認しておく必要があります。
まとめ
・指定物質とは、公共用水域に多量に排出されると人の健康や生活環境に被害のおそれがある物質
・「事故時の措置」の対応時のみ届出が必要
・有害物質や油とは異なる。また排水基準や構造基準はない。
・日ごろから、使用状況や政令改正などの情報収集に努めることが重要
指定物質は、水質汚濁防止法の中では、あまり聞き慣れなかったかもしれません。しかし、水質事故の未然防止を図るため、理解を深めていただければと思います。
※本記事は信頼性を保つため、環境省や自治体の一次情報を基本としていますが、法の解釈は自治体の判断により分かれることがありますので、実際の運用の際はお住いの自治体にご相談ください。
水質汚濁防止法のおススメの本は、こちらの記事が参考になります。
水質汚濁防止法の効果的な学習方法は、こちらの記事が参考になります。