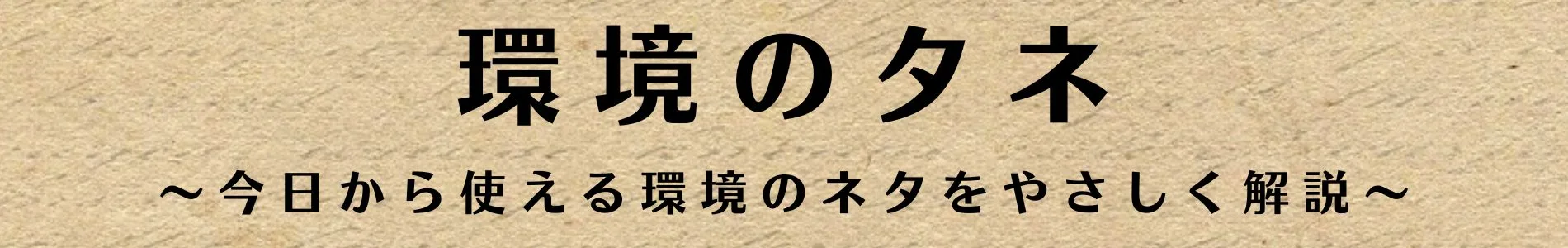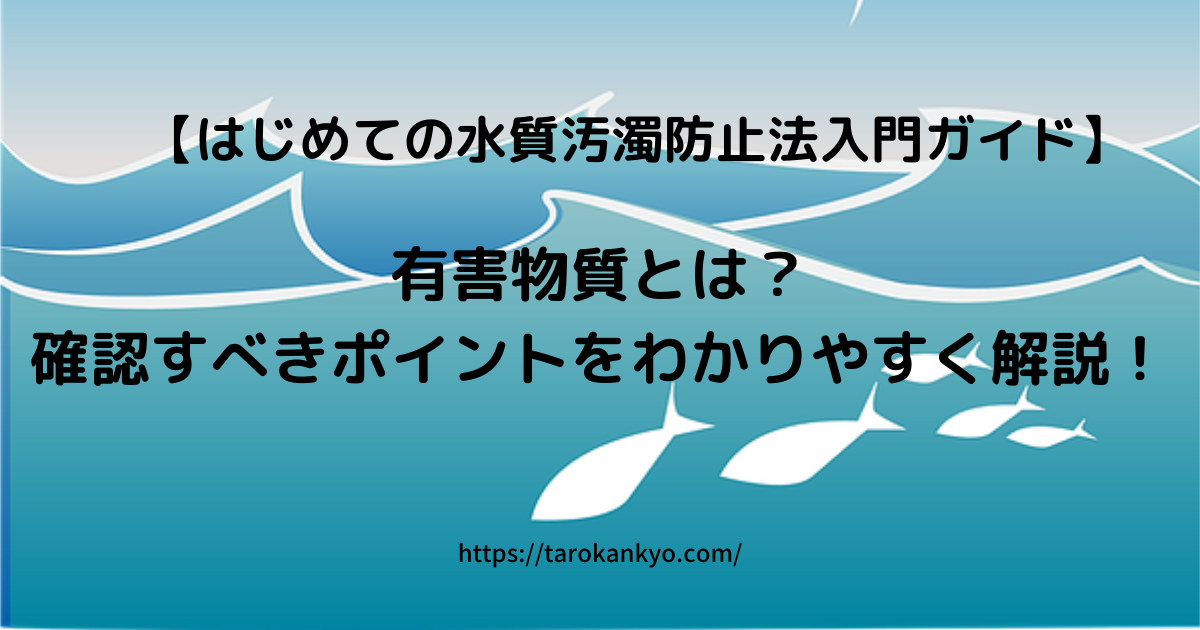水質汚濁防止法の有害物質って、一体どんなものなの?該当したら何すればいいのかな?
例えば、こんな方におすすめです
・有害物質ついて1から理解したい方
・法律や自治体のサイトを見てもよくわからない方
・企業で、新しく水質汚濁防止法の届出担当者になった方
・新しく特定事業場の経営者・工場長になる方
・公害防止管理者を受検する予定の方 など
さらに本記事は、信頼性を保つため、環境省や自治体の一次情報を基本としています。
この記事を読み終わった後は、有害物質が理解できて、具体的に何をしたらいいのかわかるようになっていると思います。
※なお、実際の法的な解釈は自治体の判断により分かれることがありますので、お住いの自治体にご相談ください。
- 水質汚濁防止法の有害物質とは?
- 有害物質について担当者が確認すべきポイント
水質汚濁防止法の有害物質
有害物質一覧
水質汚濁防止法に定義される有害物質とは、法第2条第2項第1号にあるとおり、「人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質」のことです。
具体的には、以下の28物質が定義されています。
| 1 | カドミウム及びその化合物 |
| 2 | シアン化合物 |
| 3 | 有機燐化合物(ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名パラチオン)、ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名メチルパラチオン)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト(別名メチルジメトン)及びエチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。) |
| 4 | 鉛及びその化合物 |
| 5 | 六価クロム化合物 |
| 6 | 砒素及びその化合物 |
| 7 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 |
| 8 | ポリ塩化ビフェニル |
| 9 | トリクロロエチレン |
| 10 | テトラクロロエチレン |
| 11 | ジクロロメタン |
| 12 | 四塩化炭素 |
| 13 | 一・二―ジクロロエタン |
| 14 | 一・一―ジクロロエチレン |
| 15 | 一・二―ジクロロエチレン |
| 16 | 一・一・一―トリクロロエタン |
| 17 | 一・一・二―トリクロロエタン |
| 18 | 一・三―ジクロロプロペン |
| 19 | テトラメチルチウラムジスルフイド(別名チウラム) |
| 20 | 二―クロロ―四・六―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(別名シマジン) |
| 21 | S―四―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ) |
| 22 | ベンゼン |
| 23 | セレン及びその化合物 |
| 24 | ほう素及びその化合物 |
| 25 | ふつ素及びその化合物 |
| 26 | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 |
| 27 | 塩化ビニルモノマー |
| 28 | 一・四―ジオキサン |
水質汚濁防止法施行令(カドミウム等の物質)
e-gov 水質汚濁防止法施行令
第二条 法第二条第二項第一号の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
一 カドミウム及びその化合物
二 シアン化合物
三 有機燐りん化合物(ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名パラチオン)、ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名メチルパラチオン)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト(別名メチルジメトン)及びエチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。)
四 鉛及びその化合物
五 六価クロム化合物
六 砒ひ素及びその化合物
七 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
八 ポリ塩化ビフェニル
九 トリクロロエチレン
十 テトラクロロエチレン
十一 ジクロロメタン
十二 四塩化炭素
十三 一・二―ジクロロエタン
十四 一・一―ジクロロエチレン
十五 一・二―ジクロロエチレン
十六 一・一・一―トリクロロエタン
十七 一・一・二―トリクロロエタン
十八 一・三―ジクロロプロペン
十九 テトラメチルチウラムジスルフイド(別名チウラム)
二十 二―クロロ―四・六―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(別名シマジン)
二十一 S―四―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ)
二十二 ベンゼン
二十三 セレン及びその化合物
二十四 ほう素及びその化合物
二十五 ふつ素及びその化合物
二十六 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物
二十七 塩化ビニルモノマー
二十八 一・四―ジオキサン
有害物質とは具体的にどんな物質?
水質汚濁防止法では分類されていませんが、おおまかには3つに分けられます。これらの項目はもともと、環境基本法の環境基準に定められている項目です。
カドミウム、鉛、六価クロム、水銀、シアン、ヒ素、フッ素、ホウ素、アンモニア及び硝酸化合物等、セレン
トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、一・二―ジクロロエタン、一・一―ジクロロエチレン、一・二―ジクロロエチレン、一・一・一―トリクロロエタン、一・一・二―トリクロロエタン、一・三―ジクロロプロペン、ベンゼン、塩化ビニルモノマー、一・四―ジオキサン
有機りん化合物、ポリ塩化ビフェニル(PCB)、チウラム、シマジン、チオベンカルブ
※ 土壌汚染対策法の特定有害物質とは異なります。
各有害物質の用途、環境や人体への影響については、環境省の化学物質ファクトシートをご覧ください。
Q 硝酸や希硝酸・アンモニア・尿素・4 級アンモニウム塩は有害物質に該当するのか?
A 硝酸、希硝酸・アンモニアは水質汚濁防止法では有害物質に該当します。なお、それらの化合物である硝酸ナトリウムや塩化アンモニウム等も有害物質に該当します。尿素・4 級アンモニウム塩は該当しません。
(出典:大阪市建設局QA)
有害物質と指定物質の違い
水質汚濁防止法第2条第4項に「指定物質」というものが定義されていますが、有害物質とは別の物質です。
指定物質は「公共用水域に多量に排出されると人の健康や生活環境に被害を及ぼすおそれがある物質」であり、排水基準や構造基準といった規制はかかりません。必要な手続きは「事故時の措置の届出」のみです。
| 一 ホルムアルデヒド |
| 二 ヒドラジン |
| 三 ヒドロキシルアミン |
| 四 過酸化水素 |
| 五 塩化水素 |
| 六 水酸化ナトリウム |
| 七 アクリロニトリル |
| 八 水酸化カリウム |
| 九 アクリルアミド |
| 十 アクリル酸 |
| 十一 次亜塩素酸ナトリウム |
| 十二 二硫化炭素 |
| 十三 酢酸エチル |
| 十四 メチル―ターシヤリ―ブチルエーテル(別名MTBE) |
| 十五 硫酸 |
| 十六 ホスゲン |
| 十七 一・二―ジクロロプロパン |
| 十八 クロルスルホン酸 |
| 十九 塩化チオニル |
| 二十 クロロホルム |
| 二十一 硫酸ジメチル |
| 二十二 クロルピクリン |
| 二十三 りん酸ジメチル=二・二―ジクロロビニル(別名ジクロルボス又はDDVP) |
| 二十四 ジメチルエチルスルフイニルイソプロピルチオホスフエイト(別名オキシデプロホス又はESP) |
| 二十五 トルエン |
| 二十六 エピクロロヒドリン |
| 二十七 スチレン |
| 二十八 キシレン |
| 二十九 パラ―ジクロロベンゼン |
| 三十 N―メチルカルバミン酸二―セカンダリ―ブチルフエニル(別名フエノブカルブ又はBPMC) |
| 三十一 三・五―ジクロロ―N―(一・一―ジメチル―二―プロピニル)ベンズアミド(別名プロピザミド) |
| 三十二 テトラクロロイソフタロニトリル(別名クロロタロニル又はTPN) |
| 三十三 チオりん酸O・O―ジメチル―O―(三―メチル―四―ニトロフエニル)(別名フエニトロチオン又はMEP) |
| 三十四 チオりん酸S―ベンジル―O・O―ジイソプロピル(別名イプロベンホス又はIBP) |
| 三十五 一・三―ジチオラン―二―イリデンマロン酸ジイソプロピル(別名イソプロチオラン) |
| 三十六 チオりん酸O・O―ジエチル―O―(二―イソプロピル―六―メチル―四―ピリミジニル)(別名ダイアジノン) |
| 三十七 チオりん酸O・O―ジエチル―O―(五―フエニル―三―イソオキサゾリル)(別名イソキサチオン) |
| 三十八 四―ニトロフエニル―二・四・六―トリクロロフエニルエーテル(別名クロルニトロフエン又はCNP) |
| 三十九 チオりん酸O・O―ジエチル―O―(三・五・六―トリクロロ―二―ピリジル)(別名クロルピリホス) |
| 四十 フタル酸ビス(二―エチルヘキシル) |
| 四十一 エチル=(Z)―三―[N―ベンジル―N―[[メチル(一―メチルチオエチリデンアミノオキシカルボニル)アミノ]チオ]アミノ]プロピオナート(別名アラニカルブ) |
| 四十二 一・二・四・五・六・七・八・八―オクタクロロ―二・三・三a・四・七・七a―ヘキサヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン(別名クロルデン) |
| 四十三 臭素 |
| 四十四 アルミニウム及びその化合物 |
| 四十五 ニツケル及びその化合物 |
| 四十六 モリブデン及びその化合物 |
| 四十七 アンチモン及びその化合物 |
| 四十八 塩素酸及びその塩 |
| 四十九 臭素酸及びその塩 |
| 五十 クロム及びその化合物(六価クロム化合物を除く。) |
| 五十一 マンガン及びその化合物 |
| 五十二 鉄及びその化合物 |
| 五十三 銅及びその化合物 |
| 五十四 亜鉛及びその化合物 |
| 五十五 フエノール類及びその塩類 |
| 五十六 一・三・五・七―テトラアザトリシクロ[三・三・一・一三・七]デカン(別名ヘキサメチレンテトラミン) |
| 五十七 アニリン |
| 五十八 ペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)及びその塩 |
| 五十九 ペルフルオロ(オクタン―一―スルホン酸)(別名PFOS)及びその塩 |
| 六十 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 |
水質汚濁防止法 第2条(定義)
e-gov 水質汚濁防止法
4 この法律において「指定施設」とは、有害物質を貯蔵し、若しくは使用し、又は有害物質及び次項に規定する油以外の物質であつて公共用水域に多量に排出されることにより人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定めるもの(第十四条の二第二項において「指定物質」という。)を製造し、貯蔵し、使用し、若しくは処理する施設をいう。
有害物質の排水基準
有害物質の排水基準値は以下のとおりです。排出量によらず、すべての特定事業場に一律に適用されます。
※最新版は出典元をご確認ください。
| 有害物質の種類 | 許容限度 |
| カドミウム及びその化合物 | 一リットルにつきカドミウム〇・〇三ミリグラム |
| シアン化合物 | 一リットルにつきシアン一ミリグラム |
| 有機燐りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。) | 一リットルにつき一ミリグラム |
| 鉛及びその化合物 | 一リットルにつき鉛〇・一ミリグラム |
| 六価クロム化合物 | 一リットルにつき六価クロム〇・五ミリグラム |
| 砒ひ素及びその化合物 | 一リットルにつき砒ひ素〇・一ミリグラム |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 一リットルにつき水銀〇・〇〇五ミリグラム |
| アルキル水銀化合物 | 検出されないこと。 |
| ポリ塩化ビフェニル | 一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム |
| トリクロロエチレン | 一リットルにつき〇・一ミリグラム |
| テトラクロロエチレン | 一リットルにつき〇・一ミリグラム |
| ジクロロメタン | 一リットルにつき〇・二ミリグラム |
| 四塩化炭素 | 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム |
| 一・二―ジクロロエタン | 一リットルにつき〇・〇四ミリグラム |
| 一・一―ジクロロエチレン | 一リットルにつき一ミリグラム |
| シス―一・二―ジクロロエチレン | 一リットルにつき〇・四ミリグラム |
| 一・一・一―トリクロロエタン | 一リットルにつき三ミリグラム |
| 一・一・二―トリクロロエタン | 一リットルにつき〇・〇六ミリグラム |
| 一・三―ジクロロプロペン | 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム |
| チウラム | 一リットルにつき〇・〇六ミリグラム |
| シマジン | 一リットルにつき〇・〇三ミリグラム |
| チオベンカルブ | 一リットルにつき〇・二ミリグラム |
| ベンゼン | 一リットルにつき〇・一ミリグラム |
| セレン及びその化合物 | 一リットルにつきセレン〇・一ミリグラム |
| ほう素及びその化合物 | 海域以外の公共用水域に排出されるもの一リットルにつきほう素一〇ミリグラム |
| 海域に排出されるもの一リットルにつきほう素二三〇ミリグラム | |
| ふつ素及びその化合物 | 海域以外の公共用水域に排出されるもの一リットルにつきふつ素八ミリグラム |
| 海域に排出されるもの一リットルにつきふつ素一五ミリグラム | |
| アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 一リットルにつきアンモニア性窒素に〇・四を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量一〇〇ミリグラム |
| 一・四―ジオキサン | 一リットルにつき〇・五ミリグラム |
1 「検出されないこと。」とは、第二条の規定に基づき環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。
2 砒ひ素及びその化合物についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和四十九年政令第三百六十三号)の施行の際現にゆう出している温泉(温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第二条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。
(参考)排水基準を定める省令(昭和四十六年総理府令第三十五号)
ちなみに、排水基準項目は有害物質の定義と微妙に異なります。
・「水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物」と「アルキル水銀化合物」に分かれる
・「一・二―ジクロロエチレン」ではなく「シス―一・二―ジクロロエチレン」
・「塩化ビニルモノマー」がない(地下浸透規制のみ)
有害物質使用特定施設
有害物質を「製造・使用・処理」する特定施設を「有害物質使用特定施設」とよびます。通常の特定施設にかかる規制に加え、構造基準等の規制がかかります。
なお、有害物質使用特定施設に該当するかに、有害物質の濃度は関係ありません。
【製造】有害物質を製品として製造すること
【使用】有害物質をその施設の目的に沿って,原料,触媒等として使用すること
【処理】有害物質又は有害物質を含む水を処理することを目的として,有害物質を分解又は除去すること
【参考】法第2条第8項
有害物質貯蔵指定施設
有害物質を含む廃液など液状のものを貯蔵する目的の施設を「有害物質貯蔵指定施設」といいます。
有害物質使用特定施設と同様、構造基準等の規制対象となります。平成24年6月の法改正で新たに追加された施設です。
【参考】法第5条第3項
担当者が確認すべきポイント
使用薬品に有害物質が含まれていないか
まずは有害物質を使用しているか確認してください。使用している薬品の成分を調べ、微量でも含まれていないか調べる必要があります。
また新たに購入した薬品などに有害物質が含まれていないかなど、普段からチェック体制も整備しておくと漏れを防げます。
有害物質はどの施設でどのように扱われているか
「有害物質使用特定施設」や「有害物質貯蔵指定施設」が設置されていないか(設置する予定も含む)、確認する必要があります。
「どこで、どのように扱われているか?」によって、上記の施設に該当するか判断に迷うことも想定されるので、環境省や自治体のサイトを確認したり、直接問い合わせるなどして漏れがないようにして下さい。
環境省のこちらのサイトが参考になるはずです。
水質汚濁防止法の改正~地下水汚染の未然防止のための実効ある取組制度の創設~(平成24年6月1日施行)
届出はされているか
「有害物質使用特定施設」や「有害物質貯蔵指定施設」を新たに設置しようとする場合、もしくは構造を変更しようとする場合には、60日前までに届出が必要です。
他にも、廃止した場合(※)、(申請者の)氏名変更した場合、承継した場合にも届出が必要です(30日以内)。
なお、通常の特定施設と異なり、排出水(公共用水域へ排出される排水)の有無は関係ありません。
【参考】法第5条第1項、第3項
※有害物質使用特定施設を廃止した場合、別途、土壌汚染対策法の手続きが必要です。
構造基準を遵守しているか
「有害物質使用特定施設」や「有害物質貯蔵指定施設」の設置者は、「構造等に関する基準」の規制がかかりますので、遵守状況を確認する必要があります。
具体的には、上記施設に付帯するこんな設備に基準がかかります。
・施設の床面及び周囲
・施設に付帯する配管等
・施設に付帯する排水溝等
・地下貯蔵施設
【参考】法第12条の4、施行規則第8条の2から第8条の7
定期点検を行っているか
上記の施設の設置者は、施設の構造等について、目視等の方法により定期点検を実施し、その結果を記録し、保存する必要があります。
【参考】法第14条第5項、施行規則第9条の2の2から第9条の2の3
まとめ
・有害物質は法第2条第2項第1号に定義され、28種類ある
・有害物質と指定物質は別の物質
・有害物質の排水基準は、排水量に限らず一律に規制を受ける
・有害物質使用特定施設とは、有害物質を「製造・使用・処理」する特定施設
・有害物質貯蔵指定施設とは、有害物質を含む廃液など液状のものを貯蔵する目的の施設
・有害物質使用特定施設や有害物質貯蔵指定施設の設置者は、届出や構造基準等の義務がある
有害物質は、人の健康や生活環境に被害を及ぼすおそれのある物質です。公共用水域への流出や地下水への漏洩の未然防止を確実に図るため、理解を深めていただければと思います。
水質汚濁防止法のおススメの本は、こちらの記事が参考になります。
水質汚濁防止法の効果的な学習方法は、こちらの記事が参考になります。