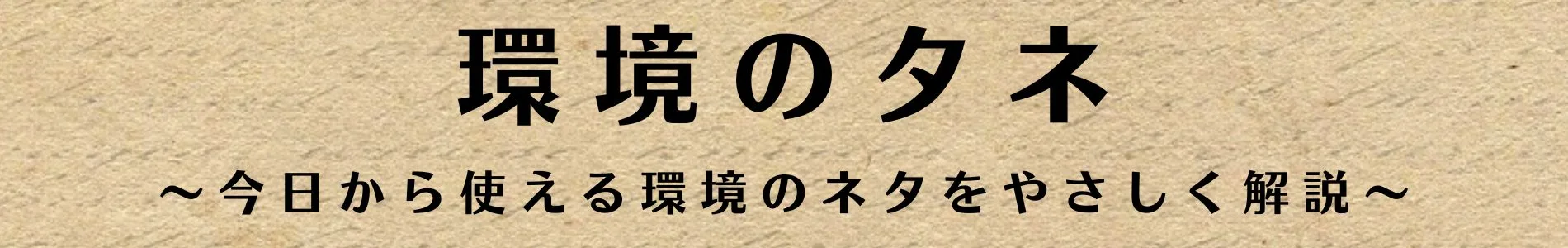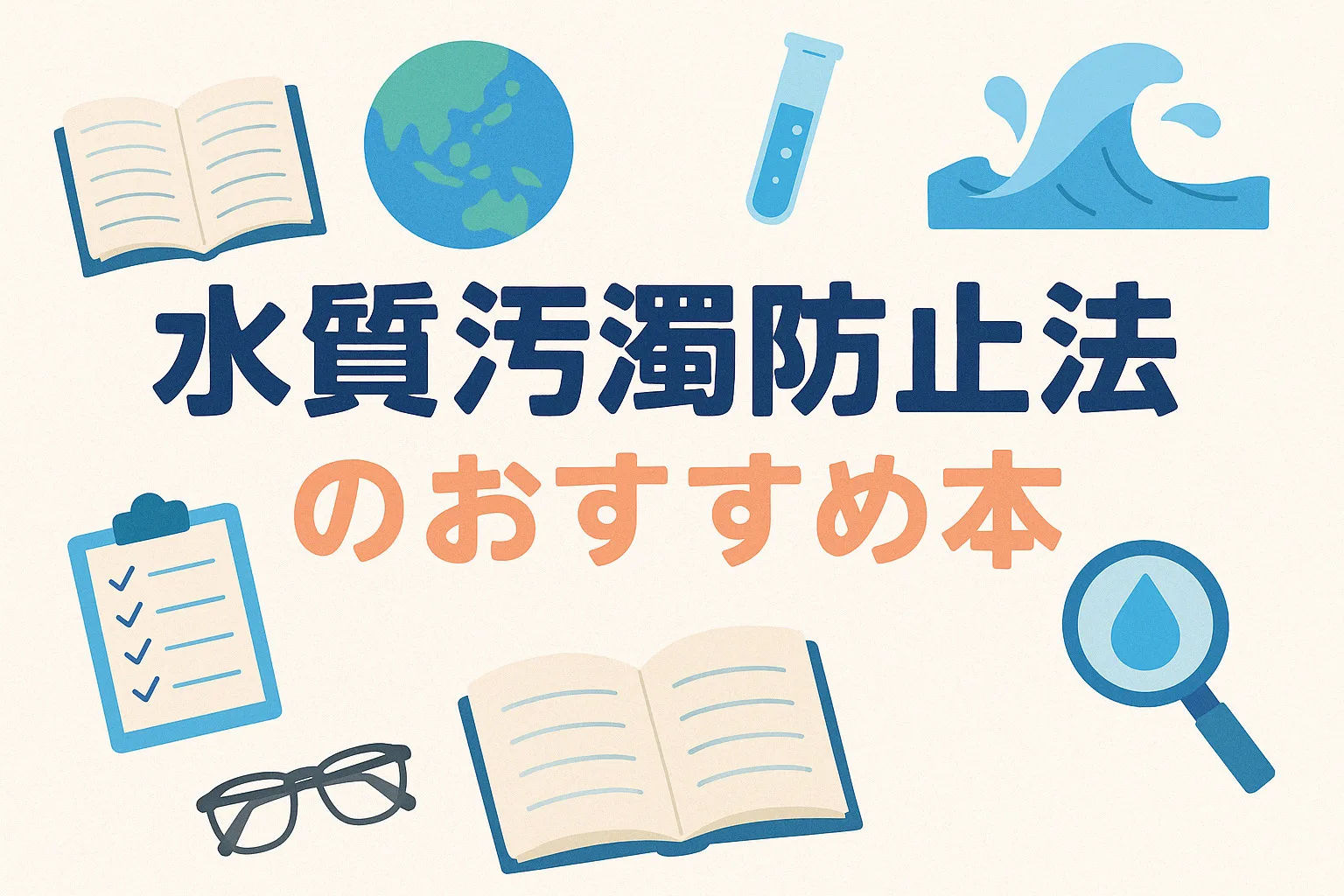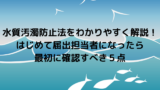水質汚濁防止法を学びたいけれど、「どの本を選べばいいのか分からない」「難しそうで手が出せない」と感じていませんか?
私はこれまで、環境行政の現場で10年以上にわたり勤務し、
水質汚濁防止法を主な担当業務として、届出審査や指導、工場への立入検査などに日常的に携わってきました。
その実務経験をふまえて、初心者でも無理なく学べる入門書から、実務や資格試験にも役立つ専門書まで、8冊を厳選してご紹介します。
・条文や制度の読み方に不安がある方でも、やさしく学べる入門書
・水質や化学の基礎知識を、法令理解に活かしたい方にぴったりの補助教材
・水質汚濁防止法の理解を深めながら、公害防止管理者試験にも活かせる参考書

目的別に紹介していますので、ぜひあなたの目的に合った一冊を見つけてください。
水質汚濁防止法をしっかり学びたい方へ
水質汚濁防止法を理解するには、まず法律の全体像を把握し、関連する技術的な背景を知ることが大切です。
とはいえ、いきなり条文を読み込むのはハードルが高い……と感じる方も多いのではないでしょうか。ここでは、初心者から実務者まで幅広く活用できる3冊の書籍をご紹介します。
どちらも国家資格「公害防止管理者(水質関係)」向けの教材として信頼性が高く、実務にも役立つ内容です。
『新・公害防止の技術と法規 水質編』(産業環境管理協会 編)
水質汚濁防止法の全体像をしっかり理解したい方には、まず手に取ってほしい一冊です。
この本は、「公害防止管理者〈水質〉」講習のために編纂された公式テキストで、法令だけでなく、排水処理や水質分析に関する実務知識まで幅広く網羅されています。
試験対策に限らず、実務や教育の現場でも活用されており、信頼性の高さは折り紙つきです。

特に、水質汚濁防止法の理解において、次のようなメリットがあります。
・法律・施行令・施行規則がまとめて掲載され、関連条文を見比べながら読み進められる
・各法令の背景やポイントが解説されており、要点がつかみやすい
・pHやBODといった排水基準の用語や意味を理解できる
・排水処理方法や水質検査の手法など、現場対応に必要な技術的内容も網羅
・環境基本法や関連法にも触れており、制度全体の中での水濁法の位置づけがわかる
・「一度しっかり学んでおきたい」という方にとって、将来の武器となる一冊
この本は、産業環境管理協会が作成する講習用の公式テキストであり、公害防止管理者の受験だけでなく、企業や自治体の研修教材、大学教材としても信頼されています。
・水質汚濁防止法を体系的に学び直したい
・工場や事業場で排水に関する法令対応をしている
・行政審査や監査での指摘に備えて知識を整理したい
・自己学習でキャリアアップを目指したい
『図解 公害防止管理者 国家試験 合格基礎講座 水質編』(産業環境管理協会 編)
「水質汚濁防止法に関心はあるけれど、どこから勉強していいか分からない」
そんな初学者の方におすすめしたいのが、こちらの図解形式の入門書です。
本書は「新・公害防止の技術と法規 水質編」と同じく、産業環境管理協会が編纂した公害防止管理者向けの公式教材です。
本書はその“入門編”にあたる内容で、図解を多く取り入れ、重要なポイントに絞った構成になっているのが特長です。

難解な法令用語や技術的な記述を避け、まずは全体像をつかみたいという方にとって、取り組みやすい一冊です。
産業環境管理協会による公式な資料でも「この本を読んでから“新・公害防止の技術と法規”に進むのが効果的」とされています。本書は2013年に出版され、最新情報には対応していませんが、学習の補助として基本となる箇所の理解には有用です。
・法令や排水のしくみを図解で直感的に理解できる構成
・項目ごとに重要ポイントが絞られており、全体像をつかみやすい
・一部の章では、実際の過去問の出題事例と解説も掲載
・図→文章→図の構成で、法律や技術の理解が自然と深まる
・もちろん、公害防止管理者の試験対策としても有効(特に初学者に適)
・水質汚濁防止法を初めて学ぶ方
・法律の文章だけではイメージが湧かないと感じている方
・公害防止管理者の受験を検討しているが、まずは基礎から入りたい方
・「新・公害防止の技術と法規」は少し難しそうと感じている方
『最短合格!公害防止管理者 超速マスター 水質編』(TAC出版)
水質汚濁防止法の基本を学びながら、
公害防止管理者〈水質関係〉の受験も視野に入れている方で、
できるだけ効率的に学習を進めたい方におすすめなのが、TAC出版の『超速マスター 水質編』です。
本書は、試験対策用に編集されたテキストですが、法律や排水処理技術などの要点がコンパクトに整理されており、制度の理解にも活用しやすい構成となっています。
章ごとにポイントをまとめたあとに確認問題が配置され、解説がわかりやすいと好評です。
なお、先にご紹介した「図解 公害防止管理者 合格基礎講座(水質編)」と構成や目的は似ていますが、こちらは直近の試験対策にも対応しており、どちらを選ぶかは学習の目的や好みに応じて決めていただいて問題ありません。いずれも、水質汚濁防止法の理解に役立つ実用的な一冊です。
・水質汚濁防止法を効率よく整理して理解したい方
・試験受検も考えながら、制度や技術も一通り学びたい方
・インプットと演習をセットで進めたい方
法令を読むのが苦手な方におすすめ
『元法制局キャリアが教える 法律を読む技術・学ぶ技術[改訂第4版]』(吉田利宏 著)
この本は、水質汚濁防止法に限らず、「法律の条文そのものを読むのが苦手…」という方のための入門書です。
法令というと、「第〇条第△項」「ただし書き」「準用する」など、独特な文体で読みづらい印象を持たれがちです。
本書では、そうした“法律文章の読み方”のコツを、元・内閣法制局キャリアの著者がわかりやすく解説しています。
「なぜこの条文はこんな言い回しなのか」「どこを読めば要点がわかるのか」といった、法律初心者がつまずきやすいポイントを丁寧に解きほぐしてくれる構成で、まさに“法律を読む技術”を磨くための一冊です。
法律そのものの解説書ではありませんが、水質汚濁防止法をきちんと読みこなしたい方にとって、読解力の土台づくりに役立つ良書です。

特に技術系の方におすすめします!私もこの本を読んだときは、もっと早くから読んでおけばよかったと後悔しました。
・法律の条文を読むのに慣れていない
・「読み飛ばしてしまう」「どこを見ればいいのかわからない」と感じている
・条文の構造や意味の拾い方を、基礎から身につけたい
・水質汚濁防止法をちゃんと読めるようになりたい
『図解でわかる!環境法・条例 ―基本のキ―[改訂2版]』(第一法規)
水質汚濁防止法は、環境基本法の下に位置づけられた「個別法」の一つです。
そのため、法律の背景や仕組みを理解するには、「環境法全体の構造」を知っておくことが大切です。
この本は、環境法の全体像をイラストと図解を交えてやさしく解説している入門書です。
法律の条文そのものを読むのではなく、制度の仕組み・役割・つながりなどをざっくりと理解したい方に向いています。
水質だけでなく、大気、土壌、廃棄物、化学物質などの関連法も網羅しており、環境行政の基本的な枠組みを学ぶには最適の一冊です。
・水質汚濁防止法の背景や仕組みを体系的に理解したい方
・環境基本法と個別法の関係を知っておきたい方
・環境法全体の構造を俯瞰して捉えたい方
・条文だけでなく、制度の“意味”や“つながり”を理解したい方
技術や化学の知識もあわせて深めたい方へ
『図解入門 よくわかる最新水処理技術の基本と仕組み[第3版]』(秀和システム)
水質汚濁防止法を理解するうえで、「排水処理技術」についての基礎知識は欠かせません。
どんな技術で汚濁物質を取り除いているのか、どのような処理方式が使われているのかを知ることで、法令の背景や実務の現場に対する理解も深まります。
この本は、排水処理の基本から、汚泥処理、膜分離技術、回収・再利用などの最新技術までを幅広くカバーした入門書です。
タイトルのとおり、図解中心でやさしく解説されているため、技術系のバックグラウンドがない方にも読みやすい構成となっています。
特に、水質汚濁防止法における排水基準と処理技術の関係をイメージできるようになる点が大きな魅力です。
「なぜこの物質の濃度を下げる必要があるのか」「処理技術の選択肢にはどんなものがあるのか」といった実務につながる視点を養いたい方に最適な一冊です。
・水質汚濁防止法の背景にある排水処理技術を学びたい方
・専門知識がなくても読みやすい図解ベースの解説本を探している方
・現場での排水処理設備やプロセスに関心がある方
・実務と法令のつながりをイメージできるようにしたい方
『図解入門 よくわかる最新分析化学の基本と仕組み[第3版]』(秀和システム)
水質汚濁防止法では、BOD(生物化学的酸素要求量)やpH、有害物質の濃度など、さまざまな「分析」が必要です。
これらの数値がどのように測定されるのか、どんな原理や手法が使われているのかを知ることは、法令の実務的な理解にも直結します。
この書籍は、分析化学の基本的な考え方から、代表的な分析手法(吸光光度法、電気化学分析、クロマトグラフィーなど)までを網羅した入門者向けの解説書です。
図とイラストでわかりやすく整理されており、「分析のことはよくわからない…」という方でもイメージしやすいと思います。
水質の項目に限らず、排水中の有害物質の測定原理や、サンプリングから前処理、分析装置の使い方など、実際の現場感覚に近い知識を得られるのが特徴です。
・BODやCODなど、水質項目の“測定のしくみ”を理解したい方
・分析化学が苦手で、やさしい解説書を探している方
・分析現場の工程や機器の使い方をざっくり把握したい方
・法令で出てくる数値の「裏側」を知っておきたい方
『一度読んだら絶対に忘れない 化学の教科書』(左巻健男 著/SBクリエイティブ)
水質汚濁防止法をしっかり理解するには、化学の基礎知識が欠かせません。
たとえば、pH・イオン・酸化還元・有機物の構造など、法令で扱われる排水基準項目の多くは高校レベルの化学に深く関わっています。
暗記や計算ではなく、ストーリー仕立てで「なぜそうなるのか」を丁寧に説明してくれるため、文系出身の方や、化学が苦手だった方にも好評です。
また、「理系っぽい難しい言葉を使わない」「身近な例を使って説明する」など、著者・左巻健男氏ならではのやさしい語り口で構成されており、初学者の“わからない”をそのままにしない配慮が感じられる内容です。
水質汚濁防止法に限らず、廃棄物処理法や大気汚染防止法、危険物取扱法など環境分野全般で役立つ“ベースとなる化学力”を養える一冊です。

この本は、“化学の基礎を学び直したい”方に向けて読みやすく整理された1冊です。かなり売れているようです。
・化学の基本から、しくみや背景まで理解したい方
・「学生時代に化学が苦手だった」という社会人・技術職の方
・排水基準や有害物質の意味をきちんと理解できるようにしたい方
・環境法を読むうえで、化学の知識に不安がある方
【番外編】行政職員も愛用する“本当の定番書”
『逐条解説 水質汚濁防止法』(中央法規出版)
『逐条解説 水質汚濁防止法』という本をご存じでしょうか?
この本は、水質汚濁防止法を担当する行政職員などが愛用する定番中の定番といえる一冊です。
タイトル通り、「条文ごとに趣旨・背景・改正履歴などを丁寧に解説」した構成で、条文一つ一つを解説したものであり、行政職員が法の解釈や運用に活用するものです。
1996年出版で、現在は入手困難な状況ですが、中古市場などで見つけたら確保しておく価値は十分あります。
重厚な内容のため初学者向けとは言えませんが、水質汚濁防止法をマスターをしたい方には一読の価値があります。
まとめ|自分に合った1冊を、まずは手に取ってみてください
ここまで、水質汚濁防止法の理解に役立つ本を8冊ご紹介してきました。
法令そのものにしっかり向き合いたい方、仕組みをざっくり把握したい方、そして技術や化学に苦手意識がある方まで、それぞれのニーズに合った1冊が見つかれば幸いです。
「法律って難しそう」「どれを選べばいいかわからない」と感じるかもしれませんが、まずはとっつきやすそうな1冊から、気軽に読み始めることが大切です。

私自身も最初は条文を読むのに苦労しましたが、
こうした本をうまく使うことで、法律の仕組みが少しずつ見えてきました。
自分のペースで大丈夫です。気になった本から始めてみてくださいね。